「後継者がいない」「経営の先行きが不安」「新規出店したいけどリスクが大きい」というお悩みを抱える歯科医師は年々増えています。
近年、こうした課題の解決策として注目されているのが「歯科M&A(合併・買収)」です。個人開業医から医療法人まで、売却・譲渡や事業拡大の手段としてM&Aを選ぶケースが増加しています。
本記事では、歯科M&Aの基本的な仕組みから、相場、実際の事例、メリット、成功のポイントまでをわかりやすく解説します。将来に向けて確かな選択をしたいと考えている方は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。
歯科M&Aとは
歯科M&Aとは、歯科医院や企業の間で経営権や事業を譲渡・売買・合併する取引のことです。
後継者不在や経営の効率化、事業拡大を目的に、近年多くの医院で導入が進んでいます。
主な手法には、事業譲渡・株式譲渡・合併・分割・居抜き売却などがあり、目的や状況に応じて選択されます。
後継者問題の解決や経営基盤の強化、リスク分散などの利点がある一方で、医療法などに基づく手続きや専門家の支援が不可欠です。既存の患者やスタッフを引き継げるため、短期間で安定した事業運営が可能となります。売却側は廃業を避けながら、経済的利益を得られます。
歯科M&Aの相場と費用
歯科M&Aの売却価格は、一般的に2,000万〜3,000万円が中心です。
規模や立地により500万〜4,000万円の幅があり、都市部の大規模医院では1億円を超えることもあります。
価格は「時価純資産」+「営業権(営業利益の0〜3年分)」で算出するのが一般的です。個人医院は営業利益0〜1年分、医療法人は2〜3年分を加算します。
費用面では、売却価格に加えて仲介手数料(譲渡額の5〜10%)、着手金や中間金、弁護士・会計士などの専門家費用がかかります。たとえば譲渡価格が2,000万円なら、仲介手数料は200万〜300万円が目安です。
新規開業に比べて初期投資を抑えられる点がM&Aの大きなメリットです。費用体系や支払い条件は事前に確認しましょう。
歯科M&Aの成功事例
歯科M&Aは、事業承継や成長戦略の手段として注目を集めていますが、実際にどのような成果が得られるのかを知ることは、検討を進めるうえで重要です。歯科M&Aの成功事例は以下のとおりです。
以下では、実際の成功事例をもとに、歯科M&Aがもたらす具体的な効果やメリットについて紹介します。
事例1:愛知県の医療法人が地域密着型の歯科技工所を買収
愛知県で複数の歯科医院を展開する医療法人が、日進市にある地域密着型の歯科技工所(有限会社クラフト)を買収しました。目的は、地域ネットワークの拡大、技工キャパシティの強化、技工士不足への対応です。
歯科技工業界は参入障壁が高く、長年の信頼や顧客基盤を持つ技工所の買収は、事業拡大の大きな足掛かりとなります。買収後も所長が10年間勤務を継続する契約を結び、技術や取引関係の円滑な引継ぎが実現しました。
譲渡金額は700万円(うち仲介手数料300万円)で、売り手には退職金として400万円が支払われました。負債は保険解約で清算され、買い手側の負担はありません。
この買収により、地域との信頼関係や技工士の技術力を維持したまま、グループ全体の受注増加と技術連携が進みました。新規参入に比べて低コストでの事業拡大も実現しており、M&Aの成功事例といえます。
事例2:東北地方で5院以上を展開する歯科医療法人が投資ファンドへM&Aを実施
東北地方で5院以上を運営し、スタッフ100名超・年商約10億円を誇る大型歯科医療法人が、投資ファンドへのM&Aを実施しました。スキームは出資持分譲渡と吸収合併を組み合わせた形式です。
理事長は40代で、さらなる事業拡大と従業員の安定を目指す中、経営負担や将来のキャリアを見据えてM&Aを決断しました。個人資産の形成や自由な働き方の実現も動機の一つです。
譲渡後は3年間の継続勤務契約を締結し、週4日勤務や長期休暇の取得など柔軟な勤務形態を実現。経営からは一歩退きつつ、専門性を活かして臨床に集中できる環境を整えました。
このM&Aにより、法人は地域No.1から全国展開への基盤を確保し、従業員の雇用も安定しました。
参考:日本歯科医療投資株式会社「M&Aで歯科医院の大型売却に成功した事例」
歯科M&Aでおすすめの仲介会社
歯科M&Aを進めるうえで、仲介会社の選定は成功の可否を大きく左右します。実績や専門性、サポート体制は会社ごとに異なるため、自院の状況に合ったパートナー選びが重要です。
歯科M&Aでおすすめの仲介会社は、以下のとおりです。
以下では、歯科M&Aに強みを持つ仲介会社について、それぞれの特徴を紹介します。
複数の仲介会社の実績や対応力、費用などを比較・検討したい場合は、「M&A比較ナビ」を活用するのが効率的です。
歯科M&Aを検討中の医院経営者の方は、まずは実績豊富な仲介会社や、M&A比較ナビなどの比較サービスを活用し、納得のいくパートナー選びから始めることをおすすめします。
株式会社サイヨウブ(MAポート)

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 対応地域 | 全国 |
| 実績 | 年商0円の個人事業主や債務超過企業のM&A実績あり |
| 特徴および強み | ・年商1,000万円~10億円程度の中小企業中心にM&A支援 ・幅広い業種のM&Aに対応 ・公認会計士・弁護士など各専門家によるチーム体制 ・成約まで完全無料で利用できる成功報酬制 |
| 料金 | ・着手金:無料 ・中間報酬:無料 ・成功報酬:レーマン方式、最低報酬額150万円 |
| 運営会社 | 株式会社サイヨウブ |
| 公式サイトURL | https://www.maport.jp/ |
株式会社サイヨウブ(MAポート)は、歯科医院専門のM&A仲介会社で、完全成功報酬制を採用しています。着手金は不要で、成約時のみ報酬が発生する明確な料金体系が特徴です。
公認会計士や弁護士など専門家チームが在籍し、価格算定からPMIまで一貫して対応します。最短21日での成約実績もあり、スピードと交渉力が強みです。
相談のしやすさや丁寧な対応が高く評価されており、初めてM&Aを検討する歯科医院にも適した仲介会社です。
日本歯科医療投資株式会社

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 対応地域 | 全国 |
| 実績 | 20院を超える歯科医院のM&A支援実績 |
| 特徴および強み | ・日本初の現役歯科医師によるM&A仲介 ・歯科医院特化型M&Aの提案力 ・コネクションを通じて双方に有利な機会を提供 |
| 料金 | 要問い合わせ |
| 運営会社 | 日本歯科医療投資株式会社 |
| 公式サイトURL | https://nihon-dental-investment.com/ |
日本歯科医療投資株式会社は、現役歯科医師が代表を務める歯科医院専門のM&A仲介会社です。累計支援額は80億円を超え、業界トップクラスの実績を誇ります。
歯科医師ならではの視点で、売却・承継の双方をサポートしており、価格算定や交渉支援はもちろん、成約後のPMIや採用支援まで一貫して対応します。
専門家チームによる実務力と、現場目線の丁寧な支援が強みです。初めてM&Aを検討する医院にも適した仲介会社です。
デンタルキャリア
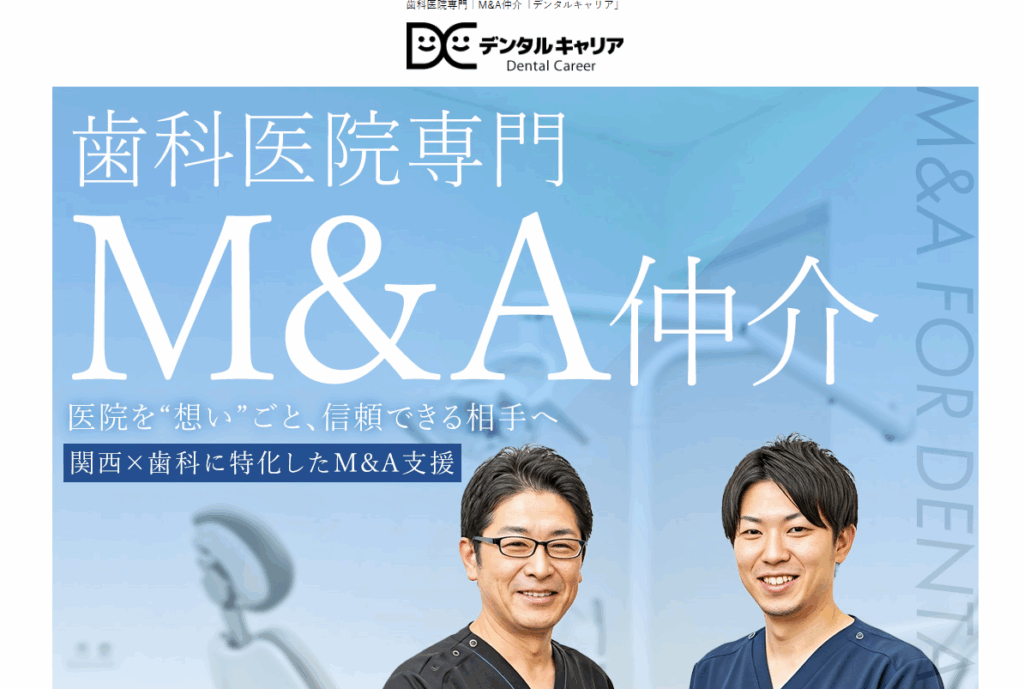
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 対応地域 | 関西中心 |
| 実績 | 地域に根差したネットワークと実績 |
| 特徴および強み | ・関西エリア中心の歯科医院専門M&A仲介サービス ・先生の想いに寄り添ったマッチング ・M&A専門の顧問弁護士と連携 |
| 料金 | ・相談:無料 ・着手金:10万円 ・中間報酬:20万円 ・成功報酬:レーマン方式、最低200万円 |
| 運営会社 | 日本歯科医療投資株式会社 |
| 公式サイトURL | https://www.dental-career.net/ma/ |
デンタルキャリアは、関西を中心に展開する歯科医院専門のM&A仲介サービスです。売却・承継・開業支援に特化し、業界経験豊富な専門チームが対応します。
地域密着型のネットワークを活かし、「顔が見える」マッチングを重視していることが特徴です。登録歯科医師・医院が多数あり、信頼性の高い紹介が可能です。法務面では顧問弁護士と連携し、契約や条件交渉も安心して進められます。
また、転職支援も手がけており、M&A後の人材確保まで一貫して対応できます。丁寧な説明と交渉力に定評があり、初めてのM&Aにも適した仲介会社です。
歯科業界におけるM&Aの必要性
少子高齢化や地域偏在、人材不足といった構造的な課題に直面するなか、歯科業界でも経営環境が大きく変化しています。とくに個人開業医にとっては、将来の見通しを立てにくい状況が続いており、事業の継続や成長に向けた新たな選択肢が必要です。
歯科業界でM&Aが必要といわれている理由は、以下のとおりです。
以下では、歯科業界においてM&Aの必要性が高まっている具体的な理由について見ていきましょう。
後継者不足・経営者の高齢化への対応
歯科医院の多くが、後継者不在と経営者の高齢化という課題に直面しています。
帝国データバンクによると、2020年時点で後継者不在率は約90%、経営者の約6割が60歳以上とされており、事業承継が進んでいない医院が大半です。
こうした状況から、廃業や閉院は増加傾向にあり、特に地方では深刻化しています。医院の存続や地域医療を守るためには、M&Aによる円滑な承継が不可欠です。経営資源を引き継ぎ、雇用や患者基盤を守る手段として、M&Aの活用が今後さらに重要になります。
参考:帝国データバンク「医療機関の倒産・休廃業解散動向調査(2024年)」
経営基盤の強化や規模拡大
歯科業界では、多院展開や法人化を進める医療法人や企業が、M&Aを活用して経営基盤の強化と規模拡大を図っています。既存医院を引き継ぐことで、患者・スタッフ・設備を活用でき、短期間で効率的に事業の拡大が可能です。
同業者間のM&Aは、ノウハウや人材の融合によるシナジー効果を生み、サービス向上や新規事業の展開にもつながります。
近年は、投資ファンドや異業種企業の参入も進み、経営ノウハウや資金が業界全体の成長を後押ししています。
地域医療インフラの維持
歯科医院の閉鎖が全国で増え続けています。経営者の高齢化や後継者が見つからない状況が要因の一つです。
とくに地方や過疎地域では、歯科医師の減少が深刻で、「無歯科医地区」が広がりつつあります。通院が難しい高齢者や要介護者にとって、歯科医院は日常の健康を支える大切な存在です。
地域の歯科医療を維持する方法として、M&Aが注目されています。後継者がいない医院でも、第三者が承継することで診療の継続が可能となり、患者の通院先やスタッフの雇用も守られます。訪問診療や地域包括ケアも維持され、地域全体の医療体制を支える手段となるでしょう。
歯科M&Aは、経営だけでなく、地域医療を守る社会的な役割も担う重要な選択肢です。
デジタル化・技術革新への対応
歯科業界では、AI診断や3Dプリンター、CAD/CAMなどの技術が急速に普及し、診療効率や精度、患者満足度の向上につながっています。
技術革新に対応するには、高額な設備投資と専門人材が必要です。
資金力のある大手法人は、M&Aを通じて小規模医院を傘下に収め、設備の共有や経営効率化を図っています。古い設備を持つ医院も、グループ参画により最新技術への対応が可能となり、競争力を高めています。
M&Aは、デジタル化に遅れず対応するための有効な手段として、今後ますます重要になるでしょう。
歯科業界のM&Aスキーム
歯科医院のM&Aで用いられる主なスキーム(取引手法)は、以下のとおりです。
それぞれのスキームには、メリット・デメリットや実施時の注意点が異なります。
以下では、代表的なスキームを解説します。
株式譲渡
株式譲渡とは、歯科医院を運営する法人(会社)の株を、買い手がそのまま引き継ぐ方法です。
株式譲渡では、医院の医業許可や、スタッフとの雇用契約、患者との関係、保有する資産や借入など、法人のすべてが新しいオーナーに引き継がれます。
経営の連続性が保てることや、スタッフや患者への影響を最小限に抑えられることがメリットに挙げられます。
一方、過去のトラブルや負債、知られていないリスクもあわせて引き継ぐことになるため、買い手側は慎重な調査が必須です。医療法人の場合は、議決権の譲渡や経営権の移管に特別な手続きが必要なこともあります。
事業譲渡
事業譲渡は、歯科医院の診療事業そのものや、設備、スタッフ、患者カルテなど必要な事業資産だけを選んで、買い手に引き継ぐ方法です。
法人全体ではなく、あくまで一部事業のみの売却となるため、買い手は不要な負債などを避けやすい点が特徴です。事業譲渡の場合、買い手側は新たに医業許可(診療所開設手続き)を取得しなければなりません。
また、スタッフの雇用や患者カルテ、設備なども新しい医院として個別に承継手続きが必要です。事業譲渡は、一部だけ譲渡したい場合や個人医院の売却に向いています。
合併
合併は、売り手と買い手のそれぞれの法人が一つになり、新しい法人として統合される方法です。
二つの医院の事業や資産、スタッフが全て統合され、事業を一体化できます。事業を一体化することで、お互いの経営資源やノウハウを組み合わせて大きな組織づくりが可能になります。
ただし、合併は登記や許認可、株主総会決議など手続きが複雑になりやすく、合併後のオペレーション統合(PMI)も大きな課題になります。
双方のリスクや負債も一緒になるため、あらかじめ十分な調査が必要です。
持分譲渡
医療法人では会社の「株式」とは異なり、「持分」という形で出資比率や経営権を表します。持分譲渡は、持分を第三者に譲ることで法人の経営権を移転する手法です。
医療法人の本体や各種許認可、スタッフなどは基本的に変わらず、「誰がオーナーか」だけが変わるイメージです。経営権の移転が比較的スムーズに進みやすい一方、持分の評価や譲渡ルールは法人ごとに異なる場合があり、事前にしっかりと条件を確認する必要があります。
また、法律により持分譲渡に制限が設けられているケースもあるため、注意が必要です。
歯科M&Aのメリット
歯科M&Aは、単なる事業承継の手段にとどまりません。売り手・買い手の双方にとって、多くのメリットがあることから、近年M&Aの活用が広がっています。歯科M&Aの主なメリットは以下のとおりです。
以下では、歯科M&Aによって得られる具体的なメリットを解説します。
買い手側:患者基盤の拡大やブランド力向上につながる
歯科M&Aにより、既存の患者データや診療実績を引き継ぐことで、初期から安定した患者数を確保できます。新規開業に比べて早期黒字化が期待でき、事業の安定にもつながります。
また、複数医院を展開することで、広い地域での患者層を取り込むことが可能です。スタッフや診療体制も引き継げるため、患者との信頼関係を維持しやすい点もメリットです。
さらに、グループ化により知名度や信頼性が高まり、ブランド価値の向上にもつながります。歯科M&Aは、患者基盤とブランド力を同時に強化できる有効な手段です。
買い手側:人材やノウハウを獲得できる
歯科M&Aでは、既存の医師や歯科衛生士、事務スタッフなどをそのまま引き継げるため、採用や育成の手間を省けます。経験豊富なチームが残ることで、スムーズな運営も可能になります。
また、地域に根ざした診療方針や経営ノウハウ、訪問診療や小児歯科などの専門性も承継できるため、買い手側のサービスの幅や質を高めることが可能です。人材とノウハウを一括で得られる点は、大きなメリットです。
売り手側:第三者への承継で医院を存続できる
歯科M&Aは、後継者がいない医院でも第三者に承継することで、廃業を避けて事業の継続が可能です。長年築いた患者との信頼関係や地域とのつながり、スタッフの雇用を守りながら医院の価値を引き継げます。
地方や過疎地域では、医院の閉鎖が地域医療の空白を生むおそれがあるため、第三者承継による存続は地域インフラの維持にもつながります。
また、M&Aによって廃業時にかかる設備処分や人件費などのコストを回避でき、譲渡益を得ることも可能です。医院の設備やノウハウも無駄にならず、新たな経営者により有効活用されます。
売り手にとっては、経済的利益だけでなく、患者やスタッフへの配慮を含めた円満な引退が実現できる点も大きなメリットです。
売り手側:廃業リスクを回避できる
歯科医院の廃業・倒産は年々増加しており、2024年は10月時点で126件と過去最多を更新しています。高齢化や後継者不在、経営環境の悪化が主な原因です。
M&Aを活用すれば、第三者への承継によって医院を存続でき、廃業にかかる医療機器の処分費やテナント原状回復費、人件費などのコストを回避できます。さらに、医院の売却益を得ることができ、引退後の資金にもなります。
医院が継続されることで、患者やスタッフの生活も守られ、地域医療の空白化も防げます。M&Aは、廃業リスクを避けながら、医院とその価値を未来へつなぐ現実的な手段です。
参考:帝国データバンク「「歯科医院」の倒産・休廃業解散動向(2024年1-10月)」
歯科M&Aのデメリット
歯科M&Aには多くのメリットがありますが、一方で注意すべきデメリットも存在します。十分な準備や対策をせずに進めてしまうと、トラブルや想定外の負担につながる可能性もあります。歯科M&Aの主なデメリットは、以下のとおりです。
以下では、歯科M&Aにおける主なリスクやデメリットを紹介します。
買い手側:スタッフが離職する可能性がある
歯科M&Aでは、経営者の交代や診療方針の変更により、スタッフが不安を感じやすくなります。勤務環境や雇用条件の変化が離職の引き金になることも少なくありません。
とくに、旧経営陣との理念や診療スタイルの違いがある場合、摩擦が生じやすく、モチベーションの低下や大量離職につながるリスクがあります。
こうしたリスクを避けるには、段階的な方針転換や丁寧な情報共有が重要です。労働条件の維持や評価制度の明確化、旧スタッフの意見を取り入れる姿勢が、離職防止につながります。M&A後の安定運営には、組織文化の融合と信頼関係の構築が欠かせません。
買い手側:患者離れやブランド毀損のリスクがある
歯科M&Aでは、院長や診療方針が変わることで、患者が不安を感じて離れるケースがあるため注意が必要です。
経営方針の変更によりスタッフが大量に離職すると、診療体制が崩れ、患者満足度の低下やさらなる流出につながります。M&A後の統合プロセス(PMI)が不十分な場合も、サービスの質が落ち、患者離れを招く要因です。
ブランド面でも、新経営陣が医院の理念やスタイルを無視して方針転換を行うと、地域で築いてきた信頼が損なわれます。急な改革や情報不足が悪評につながることもあります。
上記のようなリスクを抑えるには、段階的な統合と丁寧な説明、前院長やスタッフとの連携、地域への情報発信が不可欠です。M&A成功の鍵は、患者と信頼関係を守る姿勢にあります。
売り手側:希望条件での売却が難しい場合がある
歯科M&Aでは、売り手が希望する条件すべてを満たして売却できるとは限りません。譲渡価格や売却時期、承継後の診療方針、従業員の処遇などについて、買い手との調整が必要となり、交渉が難航するケースも少なくありません。
とくに、待遇や評価制度の変更によってスタッフの離職が発生したり、診療方針の違いから患者が離れるリスクもあるため注意が必要です。事業譲渡では労働契約が自動で引き継がれないため、再契約に伴うトラブルが起きる可能性もあります。
また、院長交代によって医院の雰囲気やブランドが変わり、地域で築いてきた信頼が損なわれることもあります。希望条件にこだわりすぎると買い手が見つからず、売却が長期化する可能性もあるため注意しましょう。
売却を円滑に進めるには、譲れない条件と柔軟に対応できる点を明確にし、現実的なバランスで交渉を進めることが重要です。
売り手側:従業員や患者に影響がある
歯科M&Aでは、売却後の変化が従業員や患者に影響を与える可能性があります。新たな経営方針や評価制度、労働条件の変更により、スタッフのモチベーションが低下し、離職につながるリスクがあります。
また、新経営陣との関係構築がうまくいかないと、職場の雰囲気が悪化し、診療の質に影響を及ぼす恐れもあるため注意が必要です。
患者にとっても、院長交代は不安の要因です。慣れ親しんだ診療方針やサービスが変わることで、他院へ転院するケースもあります。
リスクを避けるには、売却前からの丁寧な説明や、労働条件・診療方針の継続に関する明文化、新旧経営陣の連携が不可欠です。現場の混乱を最小限に抑える対応が求められます。
歯科業界のM&Aを実施する手順
歯科業界のM&Aを実施する手順は、以下の通りです。
まずは「なぜM&Aを検討するのか」を明確にします。
たとえば、後継者問題や事業拡大、経営革新などの目的が挙げられます。
目的の曖昧さは後のトラブル要因となるため、社内でしっかり共有しましょう。
M&Aの進め方やリスク、相場感などを専門家に相談します。業界に精通した仲介会社やアドバイザーを選定し、秘密保持契約(NDA)を結びます。
どの専門家に依頼すべきか迷っている方は、M&A比較ナビを使えば、複数社の比較・紹介も可能です。
M&A比較ナビなら、仲介会社のトップレイヤーを直接紹介してくれるため、安心してM&Aを実施できます。
医院の財務資料、患者数、スタッフ状況、設備内容などを客観的にまとめます。
「強み」と「課題」を明確にし、希望条件(価格、引き継ぎ内容、従業員処遇など)を整理しましょう。
専門家が匿名で候補先を紹介・選定します。
関心のある買い手候補とは、ノンネームシート(匿名資料)や企業概要書などを開示し、相互に情報交換を行います。
売り手と買い手の経営者が直接面談し、経営理念や未来のビジョン、条件などを擦り合わせます。
「人柄」や「信頼関係」も大事な判断材料です。
双方が大まかな条件(価格、支払方法、独占交渉権、従業員扱いなど)で合意した段階で、基本合意書を締結します。
この時点では法的拘束力がないことが多いですが、今後のプロセスをスムーズに進めるためにも重要なステップです。
買い手側が医院の財務、法務、労務、契約、患者カルテ、設備、資格などを詳細に調査します。
売り手側は、求められた資料や情報を速やかに提供し、疑問点には丁寧に対応しましょう。
調査結果を踏まえ、最終的な価格や条件を調整し、正式な契約書を作成・署名します。
この段階で、医師免許や開設許可移転、従業員雇用、資産名義変更などの手続き内容も詳細に決めます。
契約内容に従い、代金の支払いや医院の引き渡し、各種名義変更、登記手続きなどを完了させます。
ここで正式にM&Aが成立します。
歯科M&Aに関するよくある質問
歯科M&Aを検討するうえで、多くの医院経営者が共通して抱える疑問があります。
以下では、実際によく寄せられる質問を取り上げ、基本的なポイントを解説していきます。購入・売却の流れや費用、注意点などもまとめているため、ぜひ参考にしてみてください。
Q どんな歯科医院がM&Aで売却しやすい?
A 立地がよく、安定した収益・患者数があり、スタッフ体制や設備が整っている歯科医院はM&Aで売却しやすいです。
駅近や住宅地などの好立地にあり、安定した収益と患者数を維持している医院は、買い手にとってリスクが少なく魅力的です。また、スタッフの定着や清潔で整った設備も評価されやすい要素です。さらに、小児歯科や訪問診療など診療の幅が広い医院は、将来性が高いと判断されやすくなります。
また、トラブルや負債が少なく法人化されている医院は、スムーズに承継しやすいため、M&Aでも人気です。
Q 売却後、院長やスタッフはどうなる?
A 売却後も院長やスタッフは多くの場合、継続勤務しますが、役割や条件が変わることがあります。
院長は1~3年程度の継続勤務が一般的で、その後は引退や非常勤勤務に移行することが一般的です。経営権は買い手に移るため、診療に専念する形になります。スタッフも原則雇用継続されますが、方針や待遇の変更により離職リスクが生じることもあります。
スムーズな引継ぎには、条件の明文化と丁寧な説明が重要です。
Q 歯科M&Aでよくあるトラブルや注意点は?
A 歯科M&Aで多いトラブルは、情報の食い違い、スタッフや患者の離脱、契約の不備です。
トラブルを避けるには、仲介会社の活用や丁寧な説明が重要です。
また、売上や負債などの情報不足、急な経営方針の変更、契約内容の曖昧さが原因で、トラブルに発展するケースが多く見られます。
トラブルを回避には、事前調査・契約の明確化・関係者への丁寧な説明が欠かせません。