「後継者がいなくて、この先どうしよう…」
「長年続けてきた施設を、誰かに良い形で引き継げないだろうか」
この記事では、老人ホームのM&Aについて価格相場から成功事例、具体的な手続きの流れまでを網羅的に解説します。
この記事を読めば、M&Aが後継者不在の有効な解決策となり、従業員や入居者を守りながら事業を承継できることがわかります。
老人ホーム業界のM&Aとは
老人ホーム業界のM&Aは、後継者不在や事業拡大といった経営課題を解決するための有効な経営戦略です。
介護業界は、高齢化社会の進展により社会的な需要が高まり続ける成長市場です。しかしその一方で、介護職員の人材不足や経営者の高齢化、異業種からの参入による競争激化など、厳しい経営環境に直面しています。
こうした状況下で、M&Aは、経営者が創業者利益を確保して安心して引退する道筋をつけるとともに、従業員の雇用と入居者の生活を守りながら事業を存続させるための、極めて現実的で有力な選択肢となっています。
老人ホーム業界のM&Aと他業界との違い
老人ホーム業界のM&Aは、他業界のM&Aとの違いは「①介護保険法などの法的規制」「②『人』を最優先に考える重要性」「③行政との密な連携」です。
老人ホーム業界は事業の公共性が高く、人の生活に直接関わるため、単なるビジネスライクな取引では成り立ちません。
例えば、事業を譲渡する際には、介護保険法に基づく行政への届出や許認可の引き継ぎが不可欠です。また、M&Aによって現場の介護職員が不安を感じて離職したり、入居者の生活環境が大きく変わったりすることは、事業価値そのものを毀損しかねません。
他業界以上に、従業員の雇用維持や処遇、入居者への丁寧な説明といった人への配慮がM&Aの成否を分けるといえます。そのため、老人ホーム業界特有の事情に精通した専門家のサポートが成功の鍵を握るのです。
老人ホーム業界のM&Aの価格相場
老人ホームのM&Aにおける売却価格(企業価値)は、一般的に「時価純資産 + 営業利益の3年〜5年分」が目安とされています。
これは、会社が持つ純粋な資産価値(時価純資産)と、将来どれくらいの利益を生み出す力があるか(営業利益)を組み合わせて評価する、実態に基づいた算出方法です。
ただし、これはあくまで基本的な計算式にすぎません。実際の価格は、施設の稼働率、介護職員の定着率、建物の築年数や立地、そして地域社会からの評判といった、数字に表れにくい要素によって大きく変動します。
例えば、高い稼働率を維持し、経験豊富な職員が多く定着している施設は、買い手にとって非常に魅力的であり、相場よりも高い価格で評価される可能性があります。逆に、行政からの指導歴があったり、建物が老朽化していたりすると、評価額は下がる傾向にあります。
正確な価値を知るためには、M&Aの専門家による詳細な企業評価が不可欠です。
老人ホーム業界M&Aの最新・注目事例3選
老人ホーム業界では、大手企業による事業拡大から地域に根差した事業承継まで、さまざまな目的でM&Aが活発に行われています。
実際の事例を知ることで、M&Aがどのように活用されているかを具体的にイメージできるでしょう。
以下では、実際に行われたM&Aの事例を取り上げ、それぞれの背景や特徴を詳しく解説します。
SOMPOケア、東京建物シニアライフサポートを子会社化し首都圏の施設を強化
SOMPOケア株式会社は、東京建物株式会社の子会社である東京建物シニアライフサポート株式会社の全株式を取得し、完全子会社化しました。SOMPOケアは、介護オペレーターとして国内トップクラスの実績を持つ企業です。
このM&Aの目的は、東京建物シニアライフサポートが運営する首都圏の高品質な介護付き有料老人ホーム8ヶ所を取得し、都市部におけるドミナント戦略(特定地域への集中出店)を強化することにあります。
SOMPOケアが持つ豊富な介護ノウハウと、買収した施設のブランド力を融合させることで、さらなるサービスの質の向上と事業基盤の拡大を目指しています。大手企業がM&Aによって特定エリアでのシェアを拡大する、典型的な成功事例といえるでしょう。
学研ホールディングス、メディカル・ケア・サービスを子会社化
教育事業で知られる株式会社学研ホールディングスは、認知症介護のリーディングカンパニーである株式会社メディカル・ケア・サービスを子会社化しました。これは、異業種から介護・福祉分野への本格参入を果たし、事業の多角化を進めた事例として注目されています。
このM&Aの背景には、学研グループが持つ教育コンテンツやサービスと、メディカル・ケア・サービスが持つ介護現場のノウハウを組み合わせることで、新たな価値提供が狙いです。
具体的には、高齢者向けの学習療法やレクリエーションプログラムの開発、介護職員向けの教育研修事業など、両社の強みを活かしたシナジー効果(相乗効果)を期待しています。成長市場である介護分野へ、M&Aを通じて迅速に参入した戦略的な事例です。
日本ホスピスホールディングス、ノーザリーライフケアを子会社化
在宅ホスピス事業を展開する日本ホスピスホールディングス株式会社は、札幌市で住宅型有料老人ホームなどを運営する株式会社ノーザリーライフケアを子会社化しました。このM&Aは、既存事業との連携強化とサービス提供エリアの拡大を目的としています。
日本ホスピスホールディングスのサービスは、末期がんや難病の方を対象とした「在宅ホスピス」という専門性の高いサービスです。ノーザリーライフケアが持つ地域に根差した老人ホーム運営の基盤を活用することで、北海道エリアにおけるホスピスケアの提供体制を強化する狙いがあります。
専門特化型の企業が、M&Aによって地域ネットワークを獲得し、事業成長を加速させる好事例です。
老人ホーム業界におけるM&Aでおすすめの仲介会社・サービス3選
老人ホームのM&Aは、介護保険法や許認可の取り扱いなど、専門的な知識が不可欠です。そのため、業界に精通した信頼できるM&A仲介会社をパートナーに選ぶことが成功への近道となります。
老人ホーム業界のM&Aにおすすめの仲介会社・サービスは、以下のとおりです。
どの仲介会社に相談すべきか判断が難しい場合は、複数のサービスをまとめて比較できる「M&A比較ナビ」の活用が便利です。自分に合った支援先を見つけたい方は、まずは無料相談から始めてみてください。
【業界特化型】CBパートナーズ
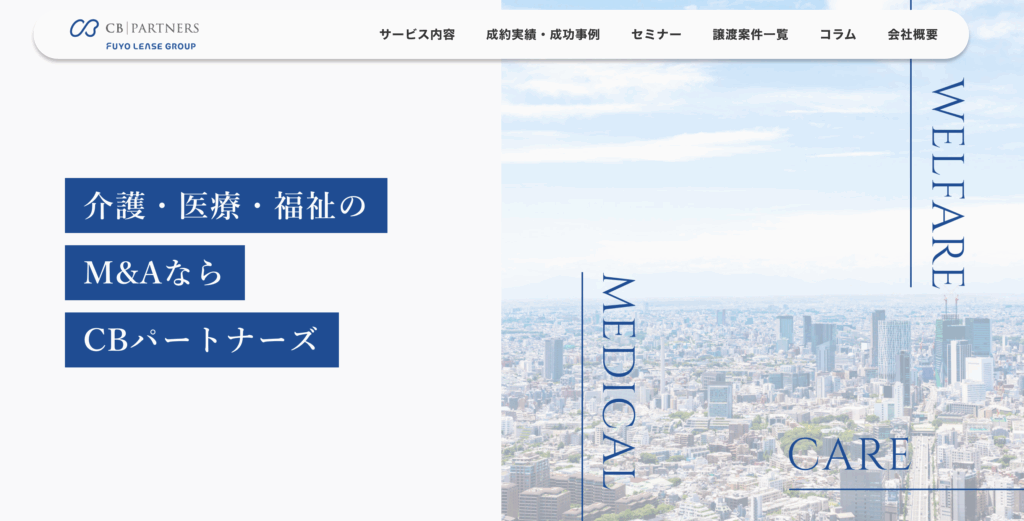
| 会社情報 | 詳細 |
|---|---|
| サポート内容 | ・売り手、買い手双方へのコンサルティング ・企業価値算定 ・マッチング ・各種交渉支援 ・契約書作成支援 |
| サポート体制 | ・介護、医療、福祉業界専門のコンサルタントによる支援 |
| 料金体系 | ・完全成功報酬制(着手金・中間金は無料) |
| 譲渡対価成功報酬の割合 | 2千万円以下の部分:10% 2千万円を超え4千万円以下の部分:9% 4千万円を超え6千万円以下の部分:8% 6千万円を超え8千万円以下の部分:7% 8千万円を超え1億円以下の部分:6% 1億円を超え5億円以下の部分:5% 5億円を超え10億円以下の部分:4% 10億円を超え50億円以下の部分:3% 50億円を超え100億円以下の部分:2% 100億円を超える部分:1% |
| 特徴 | ・介護、医療業界に特化した圧倒的な専門性と成約実績 ・未上場の優良企業やファンドとの独自ネットワーク |
| 運営会社 | 株式会社CBパートナーズ |
| URL | https://www.cb-p.co.jp/ |
CBパートナーズは、介護・医療・福祉業界のM&Aに特化した仲介会社です。業界を熟知した専門コンサルタントが、経営者の想いに寄り添いながら、事業承継から事業拡大まで一気通貫でサポートします。
最大の強みは、業界特化だからこそ可能な、きめ細やかで専門的なアドバイスです。介護保険制度の動向や行政手続き、現場の労務問題まで深く理解しているため、安心して相談できます。
完全成功報酬制を採用しており、M&Aが成立するまで費用が発生しない点も、経営者にとって大きなメリットです。介護業界ならではの悩みを抱えている方に、まず相談をおすすめしたい一社です。
CBパートナーズのアドバイザーの方は、私が抱えていた経営課題の話や将来への不安な気持ちに対して、まるで自分事のように耳を傾けアドバイスをしてくれました。
引用:公式HP
アドバイザーの方が時間をかけて丁寧に説明をしてくれたおかげで、譲渡に対する疑問や不安が解消されたとともに、未来について親身になって一緒に考えてくれるだろうという安心感に繋がりました。また、譲渡のメリットだけではなく、デメリットや苦労するポイントなども伝えてくれたことや毎回、事業所まで足を運んでくれたことも好印象でした。
引用:公式HP
CBパートナーズから、介護施設の売却打診が定期的に来ていたのが懐かしくなりました。
いつも、私の名前が少し間違っていたり・手掛けていないはずの事業内容を褒めてくださっていたりと、チャーミングなコミュニケーションでした。
引用:X(旧Twitter)
【プラットフォーム型】ブティックスM&A

| 会社情報 | 詳細 |
|---|---|
| サポート内容 | ・M&Aプラットフォームの提供 ・買い手、売り手検索 ・匿名での交渉 ・専門家による実務サポート |
| サポート体制 | ・介護業界専門のM&Aアドバイザーがサポート ・オンラインとオフラインのハイブリッド対応 |
| 料金体系 | 売り手は完全無料、買い手は成功報酬のみ |
| 成功報酬(買い手) | 成約基本料:100万円取引対価に対する料率 0円超~2,000万円以下の部分:10% 2,000万円超~4,000万円以下の部分:9% 4,000万円超~6,000万円以下の部分:8% 6,000万円超~8,000万円以下の部分:7% 8,000万円超~1億円以下の部分:6% 1億円超~5億円以下の部分:5% 5億円超~10億円以下の部分:4% 10億円超~50億円以下の部分:3% 50億円超~100億円以下の部分:2% 100億円超:1% |
| 特徴 | ・介護業界最大級のM&Aプラットフォーム ・国内最大級の介護系展示会「CareTEX」の主催による豊富な買い手候補 |
| 運営会社 | ブティックス株式会社 |
| URL | https://btix.jp/ |
ブティックスM&Aは、介護業界最大級の展示会「CareTEX」を主催するブティックス株式会社が運営するM&Aプラットフォームです。売り手は完全無料で利用でき、自社の情報を匿名で登録して、全国の買い手候補からのオファーを待つことができます。
ブティックM&Aのサービスの魅力は、圧倒的な数の買い手候補にアプローチできる点です。長年の業界ネットワークを活かし、事業拡大を目指す同業他社から、新規参入を狙う異業種の大手企業まで、多様な買い手が登録しています。
自社の価値を正当に評価してくれる相手を、効率的に探したいと考えている経営者の方にとって、非常に有効な選択肢となるでしょう。
コロナとこちらが田舎であまり直接会う機会は少なくなりましたが、スムーズに話を進めていただきました。
引用:公式HP
譲渡してからまだ落ち着いていないので仕事内容はあまり変わらずですが、譲渡先の方の対応もよく、精神的に助かっている。
引用:公式HP
大変非常識な営業電話を受けました。 話の中でこちらから何度も断っているのに、一向に切らせてくれませんでした。 こちらをバカにしたような言い回しで、本当に気分を害しました。 もちろん即着拒
引用:Google Map
【大手総合型】M&Aキャピタルパートナーズ

| 会社情報 | 詳細 |
|---|---|
| サポート内容 | ・専任コンサルタントによる初期相談からクロージングまでの一貫サポート ・企業価値評価 ・M&A戦略立案 |
| サポート体制 | ・業界専門チームと金融機関出身者による高い専門性 ・全国をカバーする営業網 |
| 料金体系 | 着手金・中間金無料の完全成功報酬制(譲渡企業側) 取引価格別手数料率(株価レーマン方式) 5億円以下:5% 5億円~10億円以下:4% 10億円~50億円以下:3% 50億円~100億円以下:2% 100億円超:1% 中間報酬:手数料総額の約10% 成功報酬:手数料総額の残り約90% |
| 特徴 | ・東証プライム上場企業による信頼性 ・豊富な成約実績・着手金無料による相談のしやすさ |
| 運営会社 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 |
| URL | https://www.ma-cp.com/ |
M&Aキャピタルパートナーズは、東証プライムに上場する大手M&A仲介会社です。幅広い業種に対応しており、もちろん老人ホームを含む介護業界のM&Aにおいても豊富な実績を誇ります。
大手ならではの信頼性と、全国を網羅する広範なネットワークが強みです。専門のコンサルタントが、企業の状況や経営者の希望を深くヒアリングし、最適なM&A戦略を提案します。
譲渡企業側は着手金が無料で、M&Aが成立するまで一切費用がかからない料金体系も安心材料です。企業の規模や業種を問わず、質の高いサポートを求める経営者の方におすすめできます。
M&Aをするにも、そのタイミングの重要性を理解し、私が目指すことに対する理解をしっかりとしていただいていたのが、M&Aキャピタルパートナーズでした。ポイントとしていたのは金額ではなく、”社員や会社が発展できる可能性”です。そして私もM&A後に残ることを前提として、どんな選択肢があるかを提案してもらいました。
引用:公式HP
担当が入口から出口まで一気通貫の体制は顧客・担当者ともに強い関係と経験を生んでいる。
引用:OpenWork
営業がしつこく困っています。
会社や自宅などに何度も手紙を送ってきます。スパムメールと同じなような行為はやめてほしいです。とりあえず消費者庁とかに連絡してみようかと思います。引用:Google Map
老人ホーム業界のM&A動向(現状・課題・今後)
老人ホーム業界のM&Aを検討するうえで、業界が今どのような状況にあり、これからどうなっていくのかを理解することは非常に重要です。
ここでは、「現状」「課題」「今後」の3つの視点から、業界の動向を解説します。
【現状】なぜ増加?老人ホームでM&Aが活発化する4つの背景
現在、老人ホーム業界ではM&Aが非常に活発化しています。
その背景には、主に以下の4つの理由があります。
- 経営者の高齢化と後継者不在
- 団塊の世代が75歳以上となるため、介護サービスの需要がさらに高まると見込まれていること
- 成長市場にビジネスチャンスを見出した、異業種からの新規参入が増加している点
- 複数の介護事業者をまとめて買収し、経営効率を高めて収益を上げる「介護ファンド」の増加
これらの要因が複雑に絡み合い、事業を売りたい経営者と事業を買いたい企業のマッチングが加速しているのが現状です。
【課題】人材不足だけではない!M&Aが進まない老人ホームに共通する課題
M&Aが進まない施設に共通した課題の中で最も深刻なのが、慢性的な「介護職員の人材不足」です。職員が定着しない施設は、サービスの質が不安定だと見なされ、買い手から敬遠されがちです。
また、建物の老朽化が進んでいるにもかかわらず、大規模な修繕や設備投資ができていないケースも課題となります。買い手にとっては、買収後すぐに多額の追加投資が必要になるため、M&Aの障壁となります。さらに、施設が賃貸物件の場合、家主がM&Aに同意せず、契約の引き継ぎができないという問題も少なくありません。
これらの課題を抱えている場合、M&Aの専門家と相談しながら、企業価値を高める努力が必要です。
【今後】大手への集約とサービスの多様化
今後の老人ホーム業界は、大手事業者への集約がさらに進むと予測されます。資本力のある大手企業がM&Aを積極的に活用し、スケールメリットを追求していく流れは続くでしょう。これにより、業界全体の経営効率は向上する可能性があります。
今後は、医療機関との連携を強化した「医療対応型」の施設や、看取りまで対応するホスピスケア、認知症専門ケアなど、質の高い専門的なサービスを提供できる施設が強く求められます。
また、ICTや介護ロボットを活用した「介護DX(デジタルトランスフォーメーション)」を進め、生産性を向上させる取り組みも不可欠です。大手への集約と、特色あるサービスの多様化という二極化が進んでいくでしょう。
老人ホーム業界におけるM&Aのスキーム
老人ホームのM&Aを進める際には、いくつかの手法(スキーム)があります。
どの手法を選択するかによって、手続きや税金、引き継がれる権利・義務が大きく異なるため、自社の状況に最も適した方法を選ぶことが重要です。
代表的な手法は以下の3つです。
【株式譲渡】運営法人ごと引き継ぐ最も一般的な手法
株式譲渡は、会社のオーナー経営者が保有する株式を買い手に売却することで、会社の経営権すべてを承継させる手法です。株式会社が運営する老人ホームのM&Aにおいて、最も一般的に用いられます。
この手法のメリットは、手続きが比較的シンプルで、事業に必要な許認可や従業員との雇用契約、各種契約関係を包括的に引き継ぐ点です。
入居者との契約もそのまま維持されるため、事業への影響を最小限に抑えられます。ただし、会社の資産だけでなく、負債や潜在的なリスク(簿外債務など)もすべて引き継がれるため、買い手は慎重なデューデリジェンス(企業調査)を行う必要があります。
【事業譲渡】赤字施設のみなど特定事業を選んで売買する手法
事業譲渡は会社全体ではなく会社の事業の一部、または全部を切り出して売買する手法です。例えば、複数の施設を運営している会社が、特定の施設だけを売却したい場合などに用いられます。
買い手にとっては、必要な資産や事業だけを選んで買収でき、不要な負債を引き継ぐリスクがないというメリットがあります。一方で、売り手にとっても、不採算事業を切り離して経営資源を集中させるといった活用が可能です。
ただし、資産や契約を個別に移転する必要があるため、手続きが煩雑になります。また、行政の許認可は再取得する必要があり、従業員とも新たに雇用契約を結び直さなければなりません。
【合併・出資持分のない法人のM&A】社会福祉法人・医療法人が経営基盤を強化する手法
老人ホームの運営主体が、株式会社ではなく社会福祉法人や医療法人である場合、M&Aの手法は大きく異なります。
これらの法人は、株式会社と違って「株式」や「出資持分」という概念がないため、営利企業のような株式譲渡によるM&Aはできません。
そのため、法人の経営権を移転する際には、「合併」や「事業譲渡」といった手法が主に用いられます。特に社会福祉法人のM&Aでは、所轄庁の認可が必要となるなど、株式会社の場合よりも複雑で厳格な手続きが求められます。
公益性の高い法人のM&Aは、地域における介護サービスの提供体制を維持・強化するために行われるケースが多く、高度な専門知識が必要です。
老人ホーム業界でM&Aを活用するメリット
M&Aは、事業を譲渡する側(売り手)と、譲り受ける側(買い手)の双方にとって、大きなメリットをもたらす可能性を秘めた経営戦略です。
それぞれの立場から、M&Aを活用するメリットを見ていきましょう。
【譲渡側】後継者問題を解決し、入居者・従業員を守りつつ個人保証も解除できる
譲渡側の経営者にとって、M&Aは深刻な後継者問題を解決し大切に育ててきた事業と、そこで働く従業員や生活する入居者を守るための最も有効な手段です。
廃業という選択肢では、従業員は職を失い、入居者は新たな施設を探さなければなりませんが、M&Aであれば事業は存続します。
さらに、経営者が会社の借入金に対して行っている個人保証や、自宅を担保に入れている状況から解放されるという、金銭的・精神的に非常に大きなメリットもあります。そして、株式や事業の売却で創業者利益(キャピタルゲイン)を得られ、引退後の豊かな生活設計を描くことが可能です。
【譲受側】許認可や人材を引き継ぎ、スピーディーにシェアを拡大できる
譲受側にとって、M&Aの最大のメリットは、新規で施設を開設する場合と比較して、圧倒的に早く事業を拡大できる点です。
土地・建物における探索と建設や行政から許認可を取得、介護職員を一から採用するには、膨大な時間とコスト、労力がかかります。M&Aであれば、すでに運営が軌道に乗っている施設と経験豊富な人材、事業に必要な許認可を一度にまとめて取得できます。
M&Aにより、スピーディーに事業規模を拡大し、サービス提供エリアでのシェアを高めることが可能です。特に、競争が激化する中で、迅速な事業展開は大きな強みとなるでしょう。
老人ホーム業界でM&Aを成功させるポイント・注意点
老人ホームのM&Aを成功に導くためには、譲渡側・譲受側それぞれが、業界特有のポイントと注意点を深く理解しておく必要があります。
ここでは、双方の立場で特に重要となる点を解説します。
【譲渡側】入居者や従業員に対する情報管理と告知のタイミングを慎重に検討する
譲渡側にとって、M&Aの成否を分ける最大の鍵は、徹底した情報管理と、関係者への告知タイミングです。
M&Aを検討しているという情報が不用意に外部へ漏れてしまうと、現場で働く従業員や、施設で生活する入居者、そしてそのご家族に深刻な不安を与えてしまいます。最悪の場合、優秀な職員の大量離職を招いたり、入居者の退去が相次いだりして、施設の事業価値そのものが大きく損なわれることになりかねません。
M&Aの交渉は、必ず秘密保持契約を結んだうえで、ごく限られた関係者のみで進めるべきです。そして、従業員や入居者へ伝える際は、M&Aの専門家と相談のうえで最適なタイミングを見計らい、誠実かつ丁寧に説明することが不可欠です。
【譲受側】行政処分歴・労務問題など、将来の運営に影響する隠れたリスクを見極める
譲受側にとって最も重要なのは、財務諸表などの数字に表れない「隠れたリスク」を、買収前のデューデリジェンス(企業調査)で徹底的に洗い出すことです。
特に注意すべきは、過去に行政から受けた指導や処分の履歴、入居者やその家族との間でトラブルや訴訟リスクの有無です。
また、未払い残業代の請求といった潜在的な労務問題も、買収後に大きな負債となり得ます。
これらのリスクを見逃してしまうと、M&A成立後に想定外の支出や対応に追われ、事業計画が根底から覆る危険性があります。弁護士や会計士などの専門家チームを組成し、法務・労務・財務の各側面から、施設の将来に影響を与えうるリスクを隅々まで調査することが、M&A成功の大前提です。
失敗しないための老人ホームM&Aの全10手順
老人ホームのM&Aは、他業界にはない特有の注意点が存在します。
ここでは、後悔しないM&Aを実現するための全10ステップを、老人ホーム業界ならではの視点を交えて具体的に解説します。
まずは「なぜM&Aをするのか」という目的を明確にします。後継者不在の解決はもちろん、「入居者と従業員の生活を守りたい」「地域に必要とされる介護サービスを存続させたい」「経営者個人の連帯保証を解除したい」など、具体的な目的を言語化することが今後の全ての判断の基礎となります。
老人ホームM&Aの成功は、パートナー選びで決まるといっても過言ではありません。介護保険制度や行政指導、介護現場の労務問題に精通した、業界特化型の仲介会社を選ぶことが極めて重要です。複数の仲介会社と面談し、実績や担当者の専門性をしっかり見極める必要があります。
もし、どの仲介会社に相談すべきか迷う場合は、複数のサービスをまとめて比較検討できる「M&A比較ナビ」で情報収集から始めるのも一つの手です。信頼できる専門家(FA)を見つけ、契約を結びましょう。
仲介会社と共に、自社の価値を客観的に評価します。その際、財務諸表の数字だけでなく、施設の稼働率、介護職員の定着率・資格保有率、行政からの指導履歴の有無といった、介護事業特有の要素が価値を大きく左右します。これらの情報を整理し、買い手に魅力を伝えるための企業概要書(IM)を作成します。
「介護への理念」を共有できる相手を探すことが重要です。同業の介護事業者だけでなく、医療法人や異業種の大手企業など、多様な買い手候補の中から、自社の文化や強みを正当に評価してくれる相手を仲介会社と選定します。情報漏洩を防ぐため、交渉は必ず秘密保持契約を結んでから開始します。
書類だけでは伝わらない「想い」を確認する重要な場です。トップ面談では、M&A後の施設長や従業員の処遇、入居者へのサービス水準の維持といった具体的な点について、相手の考え方をしっかりと確認します。ここで認識のズレがないかを確認し、基本的な条件を定めた基本合意書を締結します。
買い手が専門家を交え、施設の実態を詳細に調査します。老人ホームのDDでは、財務内容に加えて、行政からの実地指導の履歴、介護事故の発生状況、職員のサービス残業の実態といった、運営上のリスクが特に厳しくチェックされます。誠実な情報開示が、信頼関係の構築に繋がります。
M&Aの手法に応じて、介護保険法に基づく「事業者の指定変更」などの行政手続きが必要になります。特に社会福祉法人の場合は、所轄庁の認可が不可欠です。この手続きは時間がかかることも多いため、DDと並行して、仲介会社と共に計画的に行政との事前協議を進めることが肝心です。
DDの結果を踏まえ、最終的な譲渡価格や条件を確定させます。最終契約書には、施設長などキーパーソンの一定期間の引き継ぎ義務や、入居者との契約条件の維持といった、老人ホーム特有の条項を明確に盛り込むことが、後のトラブルを防ぐために重要です。
契約書の内容に基づき、株式や事業資産の移転と、売買代金の決済を行います。このクロージングをもってM&Aの取引は完了しますが、同時に、行政への最終的な届出や、従業員・入居者への正式な告知といった、デリケートかつ重要なアクションが待っています。
M&Aの真の成功は、このPMIにかかっています。特に老人ホームでは、異なる介護理念やケア方針のすり合わせ、両施設の職員同士の円滑なコミュニケーション、入居者への丁寧なサービス移行が重要になります。ここの統合プロセスを疎かにすると、職員の離職やサービスの質の低下に直結するため、慎重に進める必要があります。
老人ホームのM&Aに関するよくある質問
ここまで老人ホームのM&Aについて解説してきましたが、まだ個別の疑問や不安をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
ここでは、よくある質問とその回答をご紹介します。
- 施設が賃貸物件なのですが、M&Aは可能ですか?
-
施設が賃貸物件であってもM&Aは可能です。実際に、多くの老人ホームは建物を賃借して運営されています。ただし、その場合は、建物のオーナー(家主)から、賃借人(運営会社)が変わることについての承諾を得る必要があります。株式譲渡の場合は賃借人の名義は変わりませんが、実質的な経営者が変わるため、事前に家主へ説明し、良好な関係を築いておくことが重要です。事業譲渡の場合は、買い手が新たに賃貸借契約を結び直す必要があります。
家主との交渉や契約の引き継ぎは専門的な知見が求められるため、経験豊富な仲介会社に相談することが成功の鍵です。自社に合った仲介会社を探すなら、複数の専門家を比較できる「M&A比較ナビ」の活用も検討してみましょう。無料相談から最短1営業日で、自社に合うM&A専門家を紹介してくれます。
- M&A後、入居者へのサービス内容は変わってしまいますか?
-
M&A後も、入居者へのサービス内容や利用料金は、原則として維持されるケースがほとんどです。買い手にとっても、M&Aの目的は安定した事業を継続することにあります。そのため、既存の入居者の生活に大きな変化を与えて評判を落とすようなことは、事業上のリスクでしかありません。むしろ、大手企業の傘下に入ることで、レクリエーションが充実したり、最新の介護機器が導入されたりと、サービスが向上する可能性もあります。
ただし、最終的には契約内容によりますので、M&Aの交渉段階で入居者へのサービス方針について買い手としっかり確認しておくことが大切です。