「経営者の高齢化で後継者が見つからず、長年培ってきた技術と顧客をこのまま失ってしまうかもしれない」
「深刻な技術者不足で、太陽光発電やEV充電設備など、増え続ける新たなニーズに対応しきれない」
多くの電気工事業経営者が、後継者問題や人材不足、そして日進月歩で進む技術革新への対応などの、業界特有の課題に直面しています。こうした状況を打破し、会社と従業員の未来を守り、さらなる成長を遂げるための強力な選択肢がM&Aです。
この記事では、電気工事業界のM&Aの最新動向、価格相場、M&Aを成功させた事例、そしてM&Aを円滑に進めるための手順まで、網羅的に解説します。
電気工事業界のM&Aとは
電気工事業界のM&Aとは、企業の合併・買収を通じて、業界特有の経営課題を解決し、成長を目指す戦略的な手法です。
買い手は、有資格者をはじめとする技術者不足の解消、事業エリアの拡大、関連工事を一括受注できる体制の構築を短期間で実現することを目的とします。
一方、売り手は、深刻な後継者問題の解決(事業承継)、大手企業の傘下に入ることでの経営安定化、創業者利益の獲得、従業員の雇用維持などを目指してM&Aを選択します。
電気工事業界のM&Aと他業界の違い
電気工事業界のM&Aは、他業界と比べ有資格者と建設業許という代替困難な無形資産の価値が高い点が大きな違いです。
IT業界が技術の将来性、製造業が設備を重視するのに対し、電気工事業界では有資格者の数や経営事項審査の点数が企業価値を直接左右します。
そのため、買い手の主目的は「人材確保」、売り手は「後継者問題の解決」となるケースが多く、買収後の「技術者流出」が許認可の維持を脅かすという特有のリスクを伴います。
電気工事業界のM&Aの価格相場
電気工事業界のM&A価格相場に定価はなく、一般的に「EBITDA(営業利益+減価償却費)の4~8倍」や「時価純資産+営業利益の2~5年分」が目安とされます。
しかし最終価格は、業界特有の要素と交渉で大きく変動します。特に、第一種電気工事士などの「有資格者の人数・年齢構成」や、公共工事の受注能力を示す「建設業許可・経審点数」が企業価値を直接左右する重要な指標です。
また、再生可能エネルギー関連の実績や元請け工事の比率が高いことも評価を高める要因となり、これらの強みを持つ企業は相場以上の価格で取引される可能性があります。
電気工事業界のM&Aの成功事例
電気工事業界におけるM&Aは、後継者問題の解決という守りの一手としてだけでなく、企業の成長を加速させる攻めの戦略としても活発に活用されています。
同業者同士の統合はもちろん、異業種から参入して新たな強みを獲得するケースも少なくありません。
具体的な成功事例は、以下のとおりです。
以下では、それぞれの目的をM&Aによって達成した3つの具体的な成功事例を紹介します。
事例1. 北陸電気工事株式会社による株式会社日建の子会社化
北陸地方を地盤とする北陸電気工事株式会社が、首都圏の設備工事会社である株式会社日建を30億円で買収し、関東エリアへの本格的な事業拡大を実現しました。
北陸電気工事は、中期経営計画に掲げる関東圏での事業基盤強化を目的とし、一方の日建は業績低迷からの脱却と経営基盤の安定化を目指していました。
この統合により、北陸電気工事は日建の持つ首都圏の顧客網と管工事のノウハウを獲得したのです。両社の強みを活かし、一括受注体制の構築と競争力強化というシナジー効果を狙っています。
事例2. 燦キャピタルマネージメント株式会社による株式会社高山エンジニアリングの子会社化
このM&Aは、投資会社である燦キャピタルマネージメント株式会社が、成長著しいクリーンエネルギー分野へ本格参入するため、「特定建設業許可」を保有する株式会社高山エンジニアリングを子会社化した戦略的な事例です。
自社で許可を取得するのに要する多大な時間とコストを、M&Aによって大幅に短縮することが最大の目的でした。買収により、燦キャピタルは太陽光発電設備などの開発から施工までを一貫して行える体制を迅速に構築しました。
経営資源と技術・許認可を融合させ、事業規模の拡大を加速させることに成功したのです。
事例3. 株式会社TOKAIによる中央電機工事株式会社の完全子会社化
このM&Aは、LPガス供給など生活インフラ事業を手掛けるTOKAIグループが、事業の多角化と総合受注体制の構築を目的に、名古屋を拠点とする中央電機工事を完全子会社化した異業種参入の成功事例です。
静岡県を主戦場としていたTOKAIは、この買収によって中京圏への本格的なエリア拡大を実現しました。
さらに、既存の空調・衛生設備工事に中央電機工事の電気工事事業を加え、主要な設備工事をワンストップで提供できる体制を構築しました。両社の顧客基盤を相互活用し、グループ全体の受注機会を増やすというシナジー効果を狙っています。
電気工事業界のM&Aにおすすめの仲介会社・サービス
電気工事業界のM&Aを成功させるためには、信頼できるパートナー選びが最も重要な要素の一つです。電気工事業界のM&Aにおすすめの仲介会社・サービスは以下のとおりです。
以下では、各仲介会社を詳しく紹介します。
数ある仲介会社から自力で仲介業者を探すのが難しいと感じている方には、複数のサービスをまとめて比較検討できる「M&A比較ナビ」の活用がおすすめです。
自分に合った仲介会社を見つけるためにも、まずは無料相談から始めてみてください。
株式会社NLTEC
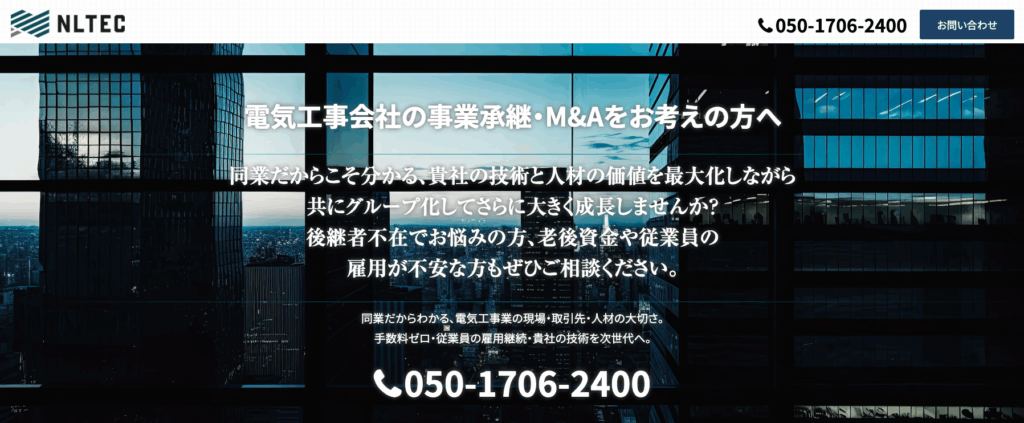
| 会社情報 | 詳細 |
|---|---|
| サービス名 | 株式会社NLTEC 事業承継・M&Aサービス |
| サポート内容 | ・電気工事会社のM&A、事業承継、グループ化の支援 ・自社が買い手となり事業を直接引き継ぐ ・譲渡後もオーナーの希望に応じた柔軟な関わり方(完全リタイア、顧問、現場スタッフ等)を提案 |
| サポート体制 | ・電気工事の専門知識を持つスタッフ(株式会社九電工出身者等)が対応 ・税理士法人と連携し、法務・税務面まで含めたスムーズな手続きをサポート ・取引先や従業員の雇用継続を重視した引継ぎ体 |
| 料金体系 | ・仲介手数料・相談料は一切不要 ・自社が買い手として事業を直接引き継ぐため、仲介手数料が発生しない |
| 特徴 | ・運営会社自身が電気工事会社であり、業界への深い理解がある ・仲介ではなく、買い手として直接事業を承継するモデル ・仲介手数料や相談料が無料 ・事業譲渡後も、オーナーの希望に応じて柔軟な関わり方が選択可能 |
| 運営会社 | 株式会社NLTEC |
| URL | https://nltec.co.jp/succession |
株式会社NLTECは、電気工事業界に特化したM&A・事業承継サービスを提供しています。
最大の特徴は、運営会社自身が株式会社九電工の出身者によって設立された電気工事の専門企業である点です。同業者ならではの深い業界知識を活かし、後継者不在や雇用継続などの経営課題を支援します。
仲介ではなく、自らが買い手として事業を直接引き継ぐビジネスモデルのため、仲介手数料や相談料は一切不要です。税理士法人とも連携し、取引先や従業員の安心を第一に考えた、スムーズで専門的な事業引継ぎを実現します。
後継者の育成をしながら徐々に経営を引き継ぐことで、取引先の不安も軽減され、円滑な承継ができました。
引用:株式会社NLTEC事例
現場に関与しながら技術を直接伝えることで、社員の不安を解消し、スムーズに世代交代できました。
引用:株式会社NLTEC事例
事業の継続性を重視し、時間をかけて後継者を育成したことで、経営移行が円滑に進みました。
引用:株式会社NLTEC事例
電気・電子・機械のM&A

| 会社情報 | 詳細 |
|---|---|
| サービス名 | 電気・電子・機械のM&A |
| サポート内容 | ・電気・電子・機械業界に特化したM&A仲介 ・サプライチェーンを意識した最適なマッチング提案 ・土地や機械設備などの資産の時価評価支援 ・中小企業庁「事業承継・引継ぎ補助金」の活用サポート |
| サポート体制 | ・大手半導体商社出身の代表による専門的コンサルティング ・ビジネスモデルや財務状況を分析し、仮説検証を繰り返す丁寧なマッチングプロセス ・国内事業会社、ファンド、海外企業など幅広いネットワークを活用 |
| 料金体系 | ・相談料・着手金:無料 ・報酬体系:完全成功報酬制(譲渡額レーマン方式) ・最低報酬額:300万円(税別) |
| 特徴 | ・エレクトロニクス分野に特化した高い専門性 ・業界水準より低価格な完全成功報酬制 ・中小企業庁の「M&A支援機関」に登録 ・商流やサプライチェーンへの深い理解に基づいたマッチング |
| 運営会社 | 大手半導体商社出身の代表が運営 |
| URL | https://electro-ma.com/ |
電気・電子・機械のM&Aは、大手半導体商社出身の代表が運営する、エレクトロニクス分野に特化したM&A仲介サービスです。
業界の商流やサプライチェーンを熟知した専門家が、質の高いコンサルティングを提供します。料金体系は完全成功報酬制で、着手金や相談料は無料です。最低報酬額も300万円からと、業界水準より低価格に設定されているのが特徴です。
中小企業庁のM&A支援機関に登録されており、事業承継・引継ぎ補助金の活用もできます。後継者不在などに悩む中小企業にとって、専門的かつ費用を抑えたM&Aを実現できるサービスです。
アドバイザリー株式会社

| 会社情報 | 詳細 |
|---|---|
| サービス名 | 電気工事・管工事会社のM&A・事業承継仲介 |
| サポート内容 | ・電気工事・管工事会社のM&A・事業承継仲介 ・事業の売却・買収に関するアドバイス ・企業価値評価、最適なM&Aプランの提案 |
| サポート体制 | ・電気工事・管工事業界に精通した専門アドバイザーが全国対応 ・豊富な成約実績に基づく独自のAIマッチングシステムを活用 |
| 料金体系 | ・相談料・着手金・月額報酬:無料 ・報酬体系:完全成功報酬制(譲渡企業の場合、基本合意契約まで費用発生なし) ・費用発生タイミング:基本合意時に中間金、最終契約時に成功報酬が発生 ・成功報酬:譲渡対価に応じたレーマン方式 |
| 特徴 | ・電気工事・管工事業界に特化 ・譲渡企業は基本合意まで費用がかからない安心の料金体系 ・平均4.6ヶ月、最短2週間というスピード成約実績 ・AI活用による高精度なマッチング ・全国対応、幅広い売上規模(3,000万円~数十億円)に対応 |
| 運営会社 | アドバイザリー株式会社 |
| URL | https://ma-advisory.co.jp/LP/electrical/ |
アドバイザリー株式会社は、電気工事・管工事業界に特化したM&A仲介会社です。後継者不在や人材不足に悩む経営者に対し、業界に精通した専門アドバイザーが全国規模でサポートを提供します。
最大の特徴は、譲渡企業(売り手)が「基本合意契約」を締結するまで費用が一切かからない完全成功報酬制を採用している点です。独自のAIマッチングシステムとネットワークを駆使し、平均4.6ヶ月、最短2週間という迅速な成約実績を誇ります。
相談料も無料のため、安心してM&Aの第一歩を踏み出せるサービスです。
電気工事業界のM&Aの動向(現状・課題・今後)
建設需要に支えられ安定しているように見える電気工事業界ですが、その内側では経営者の高齢化や深刻な人手不足、そして日進月歩で進む技術革新という大きな構造変化に直面しています。現状の取引動向や直面する課題、そして今後の展望を把握することは、業界関係者にとって重要です。
以下では、電気工事業界におけるM&Aのリアルな動向を「現状」「課題」「今後」の3つの視点から詳しく解説します。
【現状】事業承継と事業拡大が両輪、異業種も巻き込みM&Aが活発化
現在の電気工事業界では、事業承継と事業拡大という2つの目的からM&Aが活発に行われています。
後継者不在に悩む多くの中小企業が、事業と従業員の雇用を守るためにM&Aを有効な選択肢です。一方で、買い手側は同業他社を買収して施工エリアや市場シェアを拡大するだけでなく、空調や給排水設備などの関連分野の企業を買収し、複数の設備工事を一括で請け負う「事業総合化」を推進しています。
さらに、ビルメンテナンス会社やメーカーなど、異業種が工事機能の内製化を目的として参入するケースも増えており、業界の垣根を越えた再編が進んでいます。
【課題】技術者不足と2024年問題、M&Aでしか解決困難な構造的課題
電気工事業界は、構造的な課題として深刻な技術者不足に直面しています。
業界全体の高齢化と若年層の入職者減少により、特に電気工事士や電気主任技術者といった有資格者が慢性的に不足しており、2045年には数万人の担い手が不足すると予測されています。問題に追い打ちをかけるのが、残業規制が適用された「2024年問題」と、団塊世代の大量退職が目前に迫る「2025年問題」です。
これらの根深い課題は一企業の努力だけで解決することが難しく、即戦力となる技術者や有資格者を迅速に確保できるM&Aが、事業継続に不可欠な戦略となっています。
【今後】再エネ・DX対応が鍵、技術力と人材を持つ企業が業界再編の主役に
今後の電気工事業界では、「再生可能エネルギー」と「DX(デジタルトランスフォーメーション)」への対応が成長の鍵を握ります。
脱炭素化の流れを受け、太陽光発電や蓄電池、EV充電設備などの再エネ関連工事の需要が急増しており、この分野の技術や実績を持つ企業を対象としたM&Aが加速するでしょう。
また、スマートグリッドやBIM/CIMといったデジタル技術への対応も必須となり、IT企業などを買収して技術力を内製化する動きも強まります。こうした新しい市場のニーズに応えられる高度な「技術力」と、それを支える優秀な「人材」を保有する企業が、今後の業界再編を主導していくと予測されます。
電気工事業界のM&Aのスキーム
電気工事業界でM&Aを行う際には、目的や状況に応じて選択されるスキーム(手法)が異なります。電気工事業界のM&Aスキームは以下のとおりです。
適切なスキームを理解しておくことは、円滑な承継や成長戦略の実現に欠かせません。以下では、電気工事業界で用いられる代表的なM&Aのスキームについて解説します。
株式譲渡
株式譲渡は、売り手企業の株式を買い手企業に売却し、経営権を移転させる手法で、電気工事業界のM&Aで最も一般的に用いられます。
株式譲渡の最大のメリットは、会社を丸ごと引き継ぐため、事業運営に不可欠な建設業許可や公共工事の実績、取引先との契約、そして従業員の雇用関係が原則としてそのまま維持される点です。これにより、人材不足に悩む業界において有資格者や技術者をスムーズに確保でき、事業の継続性を高く保てます。
後継者不在に悩む経営者にとっては、事業承継を実現しつつ、個人保証からも解放される有効な手段です。
事業譲渡
事業譲渡は、会社の事業の一部または全部を選択して売買する手法です。
例えば「太陽光発電工事事業だけを売却する」「不採算部門のみを切り離す」といった柔軟な対応が可能です。買い手にとっては、必要な事業や資産、人材だけを選んで引き継げるため、簿外債務などの意図しないリスクを回避できるメリットがあります。
一方で、電気工事業に必須の建設業許可は引き継がれず、買い手が新たに取得する必要があります。また、従業員の雇用契約や取引先との契約も個別に結び直す必要があり、手続きが煩雑になる点がデメリットです。
会社分割
会社分割は、特定の事業部門を切り出して、新会社または既存の他社に包括的に承継させる手法です。
事業譲渡と似ていますが、資産や契約、従業員などを個別に移転させる必要がなく、手続きが比較的円滑に進む点が特徴です。電気工事業界では、成長著しい再生可能エネルギー関連の事業部門を独立させて専門性を高めたり、他社の関連事業と統合して「電気・空調・給排水」を一括で請け負える総合設備工事会社を目指せたり、戦略的な事業再編に活用されます。
ただし、法務・税務上の手続きが複雑になる側面もあります。
電気工事業界のM&Aを活用するメリット
電気工事業界におけるM&Aは、事業承継や規模拡大など、譲渡側と譲受側の双方にとって大きなメリットがあります。ここからは、譲渡側と譲受側それぞれのメリットについて詳しく見ていきましょう。
譲渡側のメリット
電気工事会社がM&Aによって会社や事業を譲渡する最大のメリットは、後継者不在の問題を解決し、事業と従業員の雇用を守れることです。
また、大手企業の傘下に入ることで経営基盤が安定し、安定的な工事受注が見込めるようになります。経営者個人にとっては、株式等の売却によって創業者利益を確保し、引退後の生活資金を得られると同時に、金融機関からの借入金に対する個人保証や担保からも解放されるため、安心してリタイアすることが可能です。
譲受側のメリット
買い手企業がM&Aを活用する最大のメリットは、深刻な人材不足が続く電気工事業界において、即戦力となる有資格者や経験豊富な技術者を一度に確保できることです。
これにより、自社で人材を育成する時間とコストを削減できます。また、他地域の企業を買収することで新たなエリアへ迅速に進出し、市場シェアの拡大が可能です。さらに、空調や通信など関連分野の企業を買収すれば、複数の工事を一括で請け負える事業の総合化を図ることができ、競争力強化と受注機会の拡大に繋がります。
電気工事業界のM&Aを実施するポイント・注意点
電気工事業界でM&Aを進める際には、専門資格を持つ技術者の継承や元請・下請との契約関係など、業界ならではのポイントに注意が必要です。また、留意すべき点は譲渡側と譲受側で異なり、それぞれの立場で適切な対応を取ることが成功につながります。
以下では、譲渡側と譲受側に分けて、電気工事業界のM&Aを実施する際の注意点を解説します。
譲渡側の注意点
電気工事会社がM&Aを成功させるには、自社の企業価値を正しく伝え、交渉を有利に進めるための事前準備が必要です。
まず、買い手側が特に重視する人材について、電気工事士などの有資格者の在籍状況や若手育成の体制を明確に示しましょう。次に、工事ごとの採算管理を徹底し、健全な財務状況をアピールすることが重要です。また、M&Aの目的を明確にし、譲れない条件の優先順位を決めておくと、交渉がスムーズに進みます。
買い手が行うデューデリジェンス(企業調査)には誠実に対応し、正確な情報を提供することが信頼関係の構築につながります。
譲受側の注意点
買い手企業がM&Aを成功させるには、買収後の統合(PMI)まで見据えた慎重な判断が求められます。
まず、デューデリジェンス(企業調査)を徹底し、財務状況はもちろん、帳簿に現れない簿外債務や、過去の談合といったコンプライアンス上のリスクがないかを厳しくチェックする必要があります。また、M&Aの最大の目的である技術者や有資格者の流出を防ぐため、企業文化の違いを理解し、従業員の処遇や労働環境に配慮した丁寧な統合プロセスを計画することが必要です。
計画を怠ると、期待したシナジー効果が得られない可能性があります。
電気工事業界のM&Aを実施する手順
電気工事業界のM&Aを実施する手順は、以下の通りです。
まず、なぜM&Aを行うのか目的を明確にします。後継者問題の解決、事業拡大、経営安定化など目的はさまざまです。
目的がはっきりすることで、交渉の際に譲れない条件と譲歩できる条件の優先順位がつけやすくなります。自社の将来像を描き、相手に求める条件を整理することが、成功への第一歩です。
M&Aは法務や税務など専門知識が不可欠なため、M&A仲介会社や金融機関などの専門家への相談が成功につながります。特に中小企業のM&Aでは、相談から成約まで一貫してサポートしてくれるM&A仲介会社が推奨されます。自社の業界や規模に合った実績を持つ、信頼できるパートナーを選びましょう。
自力で適切な専門家を探すのが不安な方は、複数の仲介会社を比較できる「M&A比較ナビ」の活用がおすすめです。目的に応じたサービスを見つけられるため、M&Aの成功にもつながるでしょう。
専門家と共に、自社の価値を客観的に評価する「企業価値評価」を行います。これは後の価格交渉の基礎となります。同時に、買い手候補に提示するための資料を準備しましょう。
会社の概要や財務状況、強みなどをまとめた「企業概要書(インフォメーション・メモランダム)」を作成し、交渉に備えます。
M&Aの目的に沿って、シナジーが見込める買い手候補をリストアップします。最初は企業名が特定されない「ノンネームシート」という資料で打診し、候補先が関心を示せば、秘密保持契約を締結したうえで詳細な企業情報を開示します。
これにより、情報漏洩を防ぎながら、効率的に交渉相手を探せるでしょう。
売り手と買い手の経営者同士が直接会い、経営理念や企業文化、人柄など、数字には表れない部分の相互理解を深めます。
トップ面談で信頼関係を築き、双方がM&Aに前向きであれば、譲渡価格やスケジュールなどの大枠を定めた「基本合意書」を締結します。ただし、この時点ではまだ法的な拘束力はありません。
基本合意後、買い手側が売り手企業の財務や法務、税務、事業内容などを詳細に調査します。これをデューデリジェンス(DD)と呼びます。
目的は、帳簿に現れない潜在的なリスク(簿外債務など)がないかを確認し、買収の最終判断を下すことです。DDの結果次第では、条件の見直しや交渉の中止もあり得ます。
デューデリジェンスの結果を踏まえ、最終的な譲渡価格や従業員の処遇、契約内容などの詳細な条件を交渉します。DDで新たなリスクが発見された場合、基本合意の段階から条件が変更されることもあります。
双方がすべての項目で納得できるまで、慎重に話し合いを進めることが重要です。
最終交渉で全ての条件が合意に達したら、法的な拘束力を持つ「最終契約書」を締結します。これによりM&Aは正式に成立します。契約書には、株式譲渡や事業譲渡に関する詳細な取り決めが記載され、締結後は原則として内容の変更や一方的な破棄はできません。
その後、対価の決済などを行い、経営権の移転が完了します。
最終契約の内容に基づき、売り手から買い手へ経営権(株式など)を移転し、買い手は譲渡対価の支払いを実行します。最終契約で定められた全ての前提条件が満たされて初めてクロージングが完了し、M&Aの一連の手続きが法的に完了します。
PMIは、M&A成立後に行われる最も重要な工程です。両社の経営方針、業務プロセス、人事制度、そして組織文化などを円滑に統合し、期待されるシナジー効果を最大化させることを目指します。
特に人材の定着が鍵となる電気工事業界では、丁寧なPMIがM&Aの成否を分けます。
M&Aが完了したら、従業員や取引先、金融機関などのステークホルダーに対して、適切なタイミングと方法で情報を開示します。
その後、買い手はPMI計画に沿って、買収した企業の技術や人材、顧客基盤を活用し、新たな事業展開や既存事業の強化を進めていきます。
電気工事業界のM&Aに関するよくある質問
以下では、電気工事業界のM&Aを進めるうえで寄せられることの多い質問とポイントを整理しています。
- M&Aで電気工事関連の許認可の引継ぎに失敗するリスクは?
-
電気工事業のM&Aでは、電気工事業登録や建設業許可の引継ぎに失敗すると、事業停止につながる重大なリスクがあります。
近年は電気工事士試験の難化など規制も厳格化しており、許認可の維持は一層重要です。よくある失敗例として、名義変更の失念や必要な技術者の不在による許可失効が挙げられます。
対策としては、デューデリジェンスで有効期限や技術者の在籍を確認し、契約に「許認可の引継ぎ完了」を条件として盛り込むことです。さらに行政手続きは専門家に任せると効果的です。
- 小規模事業者でも売却は可能ですか?
-
電気工事業界では小規模事業者でもM&Aによる売却は十分に可能です。
後継者不足や人材確保を背景に、買い手は事業規模よりも有資格者の在籍、特定の技術力、安定した顧客基盤などを重視します。特に再生可能エネルギー関連の実績は高く評価されるため、小規模でも強みをアピールできれば売却のチャンスはあります。
M&Aを成功するためには、自社の価値を正しく評価し、最適な専門家を見つけることが重要です。
適切な仲介会社を選ぶには、「M&A比較ナビ」の活用がおすすめです。複数の会社を比較しながら、ニーズに合った仲介会社に出会えるでしょう。