「ECの台頭と大手資本との競争で、実店舗だけでの成長に限界を感じている」
「後継者が見つからず、長年守ってきたのれんと従業員の将来をどうすれば良いか悩んでいる」
こうした課題は、小売業経営者が直面する深刻な問題です。消費者ニーズの多様化、人手不足、デジタル化の遅れなど、厳しい環境下で従来の手法のみでは事業の存続と発展が困難になっています。
この記事では、打開策としてM&Aに焦点を当て、最新動向や価格相場の考え方、具体的な成功事例、実行の手順までを網羅的に解説します。
小売業のM&Aとは
小売業のM&Aとは、事業の存続や成長戦略のために、他の企業を合併または買収することです。
売り手にとっては後継者不足の解決・経営の安定化・創業者利益の獲得、買い手にとっては事業規模の迅速な拡大・新規事業への参入・人材やノウハウの獲得などが主な目的です。
人口減少やECサイトの普及といった市場環境の変化を背景に、業界再編や生き残りをかけたM&Aが活発化しています。大手同士の経営統合や異業種からの参入も増えており、多様な経営課題を解決し新たな成長を目指すための重要な経営手段と位置づけられています。
小売業のM&Aと他業界の違い
小売業のM&Aは、「店舗網の拡大」が主要目的で、消費者動向に直接影響される点が他業界との違いです。
製造業やIT業界が技術や特許の獲得を重視するのに対し、小売業では好立地の店舗や商圏を一括で獲得し、事業エリアを迅速に拡大する目的でM&Aが活発に行われます。
また、景気やライフスタイルの変化が売上に直結することにより、Eコマース強化や生き残りをかけた業界再編、異業種からの参入が頻繁に見られることが特徴です。そのため、企業価値評価では店舗の立地が、事業承継では地域経済への貢献が他業界以上に重視される傾向があります。
小売業のM&Aの価格相場
小売業のM&A価格に定価はありませんが、一般的に「時価純資産+営業利益の2〜5年分」が目安です。
時価純資産は企業の資産と負債を現在の価値で評価したもので、営業利益の2〜5年分はのれん代と呼ばれ、ブランド力、顧客基盤、店舗の立地といった目に見えない将来の収益力を反映します。
ただし、これは交渉の目安にすぎません。最終的な価格は、専門家による詳細な企業価値評価(バリュエーション)を基に、シナジー効果や市場環境を考慮した当事者間の交渉で決定されます。
小売業のM&Aの成功事例
厳しい競争が続く小売業界では、生き残りと持続的な成長のため、M&Aが重要な経営戦略として活発に行われています。成功したM&Aは、企業に大きな飛躍をもたらしました。
特に注目すべき成功事例は、以下のとおりです。
以下では、それぞれの目的と成功のポイントを詳しく見ていきましょう。
事例1. ドン・キホーテホールディングスによる「ユニー」の買収
ドン・キホーテホールディングスによるユニー株式会社の買収は、リスクを抑えた「段階的アプローチ」で成功しました。
まず、ユニーの株式40%を取得して資本・業務提携を結び、ユニーの店舗を「MEGAドン・キホーテUNY」へ転換する実証実験を実施しました。その結果、売上が約2倍になるなど大きな成果を確認し、完全子会社化へ移行することとなったのです。
この手法により、ドン・キホーテ流の圧縮陳列や現場への権限移譲などのノウハウと、ユニーの強みである生鮮食品を効果的に融合させました。結果として、幅広い客層の支持を集め、ユニーの業績をV字回復させるという大きなシナジーを生み出すことに成功しました。
事例2. ローソンによる成城石井の買収
株式会社ローソンによる成城石井の買収は、株式会社成城石井のブランドと経営の自主性を尊重しつつ、ローソンの経営資源を投入することで大きな成功を収めました。
ローソンは、コンビニ業界の競争激化と消費者の高級志向への対応として、高品質な商品とブランド力を持つ成城石井を買収しました。買収後、ローソンは自社の強みである物流網や店舗開発ノウハウを提供し、成城石井の成長を後押ししたのです。
その結果、成城石井は売上・店舗数を大きく伸ばし、高い収益性を実現しました。買収時の数倍の価値向上を達成し、M&Aの理想的なシナジー効果を発揮した事例となっています。
事例3. セブン&アイ・ホールディングスによるアメリカのスピードウェイ買収
セブン&アイ・ホールディングスによるスピードウェイの買収は、米国コンビニ市場での圧倒的No.1の地位を確立するための戦略的な大型M&Aでした。
約2兆円規模の買収により、セブン&アイは米国3位のスピードウェイが持つ店舗網を獲得し、自社の店舗フォーマットを補完しました。最大の狙いは、日本で培ったフレッシュフードやプライベートブランドの商品開発ノウハウを導入し、ガソリンスタンド併設型店舗の商品力を強化することです。
巨額の投資は一時的に財務を圧迫しましたが、シナジー効果は計画を前倒しで達成し、売上高は大幅に増加。北米事業を中核とするグローバル戦略を加速させる大きな成果を上げています。
小売業のM&Aにおすすめの仲介会社・サービス
小売業のM&Aを成功させるには、複雑な交渉や価値算定を任せられる、信頼できるパートナーの存在が不可欠になります。数多くのM&A仲介会社の中から、特に小売業界で高い専門性と実績を持つと評判の会社を厳選しました。
以下では、それぞれの強みや特徴を紹介します。
仲介会社選びに不安を感じている場合は、複数のサービスをまとめて比較検討できる「M&A比較ナビ」の活用がおすすめです。
自分に合った仲介会社を見つけるためにも、まずは無料相談から始めてみてください。
株式会社M&Aフォース

| 会社情報 | 詳細 |
|---|---|
| サービス名 | 株式会社M&Aフォース |
| サポート内容 | ・M&A仲介 ・事業承継支援 ・M&A後のPMI(Post-Merger Integration)支援 ・M&A・事業承継に関する無料相談 |
| サポート体制 | ・経験豊富な高レベルのコンサルタントが複数在籍 ・東京、名古屋、大阪、福山(広島)の全国4拠点で対応 ・M&A成約後も継続的なフォローアップ |
| 料金体系 | ・完全成功報酬制 ・着手金、中間報酬、月額報酬は一切不要 ・M&Aに関する相談も無料 |
| 特徴 | ・M&A後のPMI支援に注力 ・譲受企業からのリピート率がほぼ100% ・小売業を含むほぼ全ての業種を網羅 ・高い実績を持つコンサルタントが在籍 |
| 運営会社 | 株式会社M&Aフォース |
| URL | https://www.ma-force.co.jp/ |
株式会社M&Aフォースは、着手金や中間金が一切不要の完全成功報酬制を採用するM&A仲介会社です。
後継者不足や事業拡大など、小売業が直面する多様な課題に対し、全国4拠点のネットワークを活かして最適なマッチングを実現します。特に、店舗オペレーションの統合や従業員の引継ぎが成功の鍵を握る小売業のM&Aにおいて、「成約後こそが本来の役割」という理念に基づく手厚いPMI支援は大きな強みです。
個人の年間平均成約件数8件以上を誇る経験豊富なコンサルタントが、企業の想いに寄り添い、買収後の成長まで見据えたサポートを提供。その結果、譲受企業からのリピート率はほぼ100%に達しています。
株式会社M&Aフォースの詳しい情報は、下記の記事をご確認ください。
クラリスキャピタル
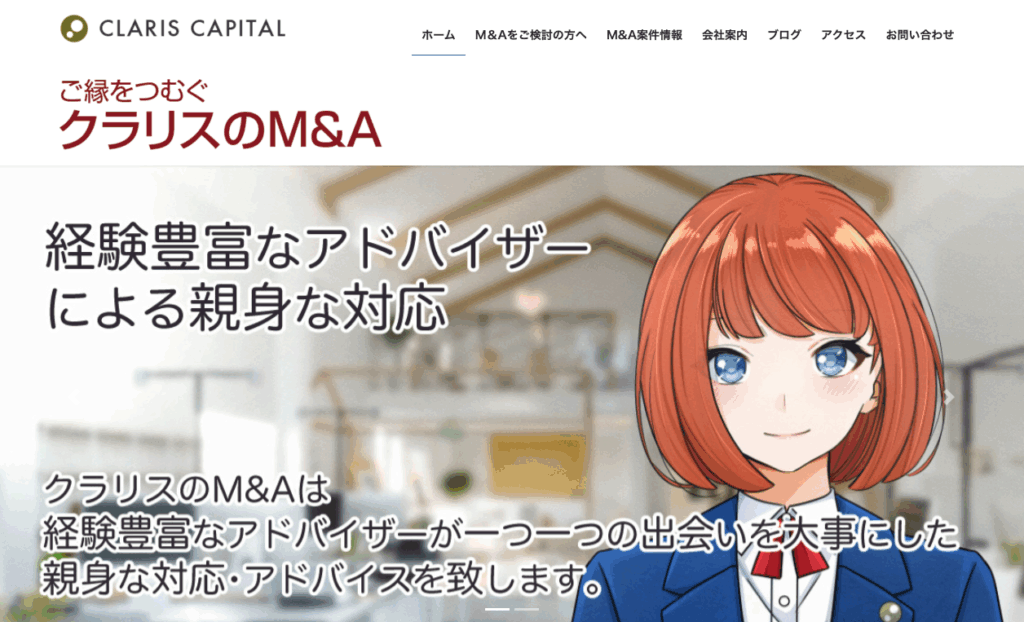
| 会社情報 | 詳細 |
|---|---|
| サービス名 | 株式会社クラリスキャピタル |
| サポート内容 | ・M&A仲介・アドバイザリー業務 ・中堅・中小企業に特化したM&A支援 ・個別相談会の実施 |
| サポート体制 | ・M&Aが成立するまで費用が発生しない料金体系で、依頼主が安心して相談できる体制 |
| 料金体系 | ・完全成功報酬制 ・着手金、中間手数料、毎月の固定報酬は一切不要 ・成功報酬は200万円からと業界最安値クラス |
| 特徴 | ・中堅・中小企業のM&Aに特化 ・小規模案件(1億円未満)にも柔軟に対応 ・分かりやすくリーズナブルな料金体系 |
| 運営会社 | 株式会社クラリスキャピタル |
| URL | https://clarisc.co.jp/ |
株式会社クラリスキャピタルは、後継者不在に悩む店舗から事業拡大を目指すチェーンまで、中堅・中小の小売業のM&Aに特化した仲介会社です。
最大の強みは、着手金や中間金が一切不要の完全成功報酬制と、成功報酬200万円からという業界最安値クラスの料金体系にあります。店舗単位の事業譲渡など、比較的小規模な案件も多い小売業にとって、このリーズナブルな設定は大きな魅力です。
初めて事業承継を考える店舗オーナーも費用リスクを心配することなく、安心して相談できます。誠実な対応をモットーに、企業の未来を豊かにするM&Aの実現を目指しています。
株式会社クラリスキャピタルについては、以下の記事で詳しく解説しているため、あわせてご覧ください。
インテグループ

| 会社情報 | 詳細 |
|---|---|
| サービス名 | インテグループ |
| サポート内容 | ・中堅・中小企業のM&A仲介・アドバイザリー業務 ・M&Aの全プロセス(案件発掘、マッチング、企業評価、交渉支援、契約書作成、クロージング支援等)をワンストップで提供 |
| サポート体制 | ・専門知識と経験を持つコンサルタントが中立的な立場でM&Aの全プロセスをサポート |
| 料金体系 | ・完全成功報酬制 ・着手金、月額報酬、中間金は原則不要 ・成功報酬は譲渡価格に応じたレーマン方式で算出(最低報酬額1,500万円) |
| 特徴 | ・中堅・中小企業のM&Aに特化 ・小売業(化粧品、寝具、スポーツ用品等)で豊富な成約実績 ・企業の想いを尊重したマッチングを重視 ・東証グロース市場上場企業としての信頼性 |
| 運営会社 | 株式会社インテグループ |
| URL | https://www.integroup.jp/industry/kouri.html |
インテグループは、中堅・中小企業のM&Aに特化した東証グロース上場の仲介会社です。小売業においても、後継者不足や成長戦略といった多様なニーズに対応した豊富な実績を有しています。
最大の強みは、着手金や中間金が一切不要の「完全成功報酬制」を採用している点です。これにより、小売業の経営者は費用リスクを抑えながら、安心してM&Aの検討を進めることができます。
企業の歴史や文化、従業員の想いを尊重したマッチングを重視しており、譲渡後も経営者が事業に関わり続けるなど、柔軟な条件交渉にも対応可能です。
今回森山様にご担当していただきました。
難しい取引先でしたが常に私達に「お任せください」と安心感を与えていただきました。
無事に締結の運びとなり大変感謝しております。本当にありがとうございました。
引用:Google Map
この度、インテグループ阿部祐輝さんには大変お世話になりました。会計事務所さんからご提案頂き、数ある中からインテグループさんなら大丈夫でしょうとのお墨付きで始まりました。10か月余りでクロージング出来ましたこと感謝いたしております。親身になって相手様とも交渉していただいたお陰で、希望通りとなり安心して引き継げました。色々とありがとうございました。
引用:Google Map
こちらにM&Aの意志など一切ないのに「営業ではありません」という口ぶりで平気で営業電話をかけてくる。代表を出すよう指名してくるが、取り次ぐわけないだろう。
引用:Google Map
インテグループの詳細については、以下の記事で解説しているため、あわせてご覧ください。
小売業のM&Aの動向(現状・課題・今後)
小売業界は、消費者のライフスタイルの変化やデジタル化の波を受け、大きな変革期にあります。生き残りと成長をかけたM&Aが活発化する中、以下では現状・課題・今後に分けて実態を解説します。業界が直面するリアルな問題を理解し、未来への戦略を探っていきましょう。
【現状】多様化する小売業界のM&A市場
小売業界のM&A市場は、業界再編や異業種参入が活発化し、多様化しているのが現状です。
人口減少による市場縮小や人手不足、ECサイトとの競争激化といった共通課題を背景に、多くの小売業者が生き残りと成長をかけてM&Aを戦略的に活用しています。
従来からある同業種間の統合による規模拡大に加え、近年は「ドラッグストアとスーパー」のように異なる強みを持つ異業種同士が連携し、新たな顧客層の開拓を目指す動きが目立ちます。これにより、事業承継問題の解決だけでなく、多様化する消費者ニーズに対応するための重要な手段としてM&A市場は変化し続けているのです。
【課題】人口減少・人件費高騰と競争激化への対応
小売業界は、人口減少・人件費高騰・競争激化という三重苦に直面しており、M&Aはこれらの課題を乗り越えるための重要な経営戦略です。
人口減少による市場縮小と後継者不足に対して、M&Aは事業の継続と新たな市場への進出を可能にします。また、人件費の高騰には、経営統合による効率化やDX推進による生産性向上が有効な対策となります。
さらに、ECサイトや異業種との競争が激化する中、M&Aを通じて他社の強みを取り込み、新たな付加価値を創造することが生き残りのポイントです。これらの課題は相互に関連しており、M&Aは複数の課題を同時に解決し得る強力な手段といえます
【今後】再編と成長の両立を目指す戦略的M&A
今後の小売業界では、生き残りをかけた再編と、新たな価値を創造する成長の両立を目指す戦略的なM&Aが一層加速します。
後継者不足や人手不足に悩む中小小売業者は、大手企業の傘下に入ることで経営基盤を安定させ、事業を存続させることが可能です。一方、成長意欲のある企業は、異業種とのM&AによってECやDXなどの新たなケイパビリティを獲得し、事業ポートフォリオを変革していきます。
M&Aは守りと攻めの両面で活用され、小売業界全体の構造変化を促す重要なドライバーとなるでしょう。
小売業のM&Aのスキーム
小売業のM&Aを成功させるためには、企業の目的や状況に応じて最適な手法(スキーム)を選択することが重要です。会社全体を包括的に承継する手法や、特定の店舗・事業のみを売買する方法など、その選択肢は多岐にわたります。
小売業のM&Aの代表的なスキームは、以下のとおりです。
以下では、それぞれの特徴を具体的に解説していきます。
株式譲渡
株式譲渡は、売り手企業の株式を買い手企業に売却し、経営権を移転させる最も一般的なM&A手法です。
小売業においては、店舗の賃貸借契約、酒類販売免許などの許認可、従業員の雇用契約などを個別に引き継ぐ必要がなく、包括的に承継できる点がメリットです。これにより、手続きが比較的簡素で事業をスムーズに継続できます。
一方で、会社を丸ごと引き継ぐため、帳簿に載っていない偶発債務などの潜在的なリスクも引き継いでしまう可能性があります。
事業譲渡
事業譲渡は、会社全体ではなく、不採算部門の整理や主力事業への集中を目的として、特定の事業や収益性の高い店舗、資産などを選別して売買する手法です。
買い手は必要な事業だけを取得でき、不要な負債を引き継ぐリスクを回避できます。しかし、小売業で重要な許認可(酒類販売免許など)は自動的に引き継がれず、買い手側で再取得が必要です。
また、店舗の賃貸借契約や従業員の雇用契約も個別に結び直す必要があり、手続きが煩雑になる点がデメリットです。
TOB(株式公開買付け)
TOB(株式公開買付け)とは、上場企業の株式を対象に、買付期間、価格、株数を公告し、市場外で不特定多数の株主から株式を買い集める株式譲渡の一手法です。
小売業では、大手企業同士の経営統合や異業種による大規模買収で用いられます。市場価格にプレミアム(上乗せ価格)を付けて買い付けることで、短期間での大量取得を目指します。
同業他社との買収合戦に発展することもあり、業界再編の引き金となるケースも少なくありません。
MBO(マネジメントバイアウト)
MBO(マネジメントバイアウト)は、会社の経営陣が、株主から自社の株式や事業を買い取って経営権を取得する手法です。
小売業においては、上場企業が短期的な株主の利益に左右されず、長期的な視点で店舗再編やDXなどの抜本的な経営改革を実行するために、株式を非公開化する目的で活用されます。
また、大手小売グループの一部門の責任者が、親会社からその事業を買い取って独立する「のれん分け」のような形での事業承継にも利用できるスキームです。
小売業のM&Aを活用するメリット
競争の激化や後継者不足、消費行動の変化など、多くの課題に直面する小売業界において、M&Aは事業の存続と成長を実現するための重要な経営戦略となっています。単なる企業の売買ではなく、双方の課題を解決し、新たな価値を創造する機会となるのです。
以下では、小売業のM&Aを活用するメリットを譲渡側と譲受側に分けて解説します。
譲渡側のメリット
後継者不在に悩む小売業経営者にとって、M&Aは事業と従業員の雇用を守りつつ廃業を回避できる有効な解決策です。
長年かけて築き上げてきた店舗やブランドを存続させられるだけでなく、不採算事業を切り離して売却し、得られた資金を主力事業に集中させる「選択と集中」も図れます。また、オーナー経営者は株式や事業の売却によって創業者利益を獲得し、リタイア後の生活資金や新たな挑戦への元手にすることが可能です。
多くの中小企業経営者が抱える金融機関からの借入に対する個人保証の重圧から解放されるという精神的・経済的な利点も大きいでしょう。
譲受側のメリット
M&Aは、新規出店や事業開発にかかる時間を大幅に短縮し、迅速に事業規模を拡大できる点が譲受側のメリットです。
すでに収益を上げている店舗や顧客基盤、確立されたブランド、さらには経験豊富な人材や運営ノウハウをまとめて獲得できます。これにより、ゼロから事業を立ち上げるリスクを抑えつつ、EC事業の強化や異業種への参入といった新たな成長戦略をスピーディーに実行することが可能になります。
加えて、仕入れの共通化によるコスト削減や、店舗網拡大によるスケールメリットを享受し、業界での競争優位性を高めることにもつながるでしょう。
小売業のM&Aを実施するポイント・注意点
小売業のM&Aを成功させるには、メリットだけでなく潜在的なリスクも理解し、慎重にプロセスを進めることが重要です。特に店舗の資産価値や従業員の引き継ぎなど、小売業特有の論点が存在します。
以下では、取引を円滑に進めて期待した成果を得るために、会社や事業を譲渡側と譲受側、それぞれの立場で注意すべきポイントを紹介します。
譲渡側の注意点
希望する条件で円滑に会社や事業を売却するためには、入念な準備と誠実な対応が不可欠です。
M&Aを検討していることが外部に漏れると、従業員の動揺や取引先の離反を招き、企業価値の低下につながる恐れがあるため、徹底した情報管理が求められます。また、少しでも有利な条件を引き出すためには、日頃から在庫の適正化や顧客データを整備し、企業価値を高めておくべきです。
譲渡価格だけでなく、従業員の雇用維持や店舗の屋号存続など、譲れない条件に優先順位をつけ、交渉の軸を明確にすることも納得のいくM&Aにつながります。
譲受側の注意点
買収後のリスクを最小化し、期待したシナジーを確実に得るためには、徹底したデューデリジェンス(買収監査)が重要です。
特に小売業では、各店舗の賃貸借契約の内容、不良在庫の有無、帳簿に載らない簿外債務などを詳細に調査し、潜在リスクを洗い出す必要があります。また、M&Aの成否を分けるのは契約後のPMI(統合プロセス)です。
異なる企業文化を持つ従業員をどう融合させるか、POSレジや在庫管理システムをどう統合するかなど、具体的な計画を事前に策定しておくことが求められます。
小売業のM&Aを実施する手順
小売業のM&Aを実施する手順は、以下の通りです。
M&Aを成功させる最初のステップは、目的を明確にすることです。譲渡側は事業承継や経営の安定化、譲受側は店舗網の拡大やEC事業の強化など、自社の課題解決につながる目的を定めます。
小売業特有の市場動向や競争環境を踏まえた上で、具体的な戦略を策定することが重要です。
M&Aは専門知識が不可欠なため、実績豊富な専門家への相談が成功のポイントです。特に小売業界に精通し、秘密保持を徹底できる信頼性の高いアドバイザーを選ぶことが重要です。
M&Aの検討が外部に漏れると、店舗スタッフや取引先に不安を与え、事業価値を損なうおそれがあります。専門家は最適な相手探しから複雑な手続きまでをサポートしてくれます。
どの仲介会社を選べば良いか迷う場合は、複数の会社を比較検討できる「M&A比較ナビ」のようなサービスを利用するのもおすすめの方法です。
策定した戦略に基づき、店舗の立地や業態、シナジー効果などを基準に候補企業を選定します。その後、経営者同士が直接会うトップ面談を行います。小売業は「人」がサービスの質を左右するため、書類だけでは分からない経営理念や企業文化の相性を確認し、信頼関係を築くことが極めて重要です。
トップ面談で双方がM&Aに前向きな意思を確認できたら、基本合意書を締結します。ここには、暫定的な買収価格や今後のスケジュール、独占交渉権などが盛り込まれます。
この時点ではまだ法的な拘束力は弱いものの、M&Aを本格的に進める上での重要な約束事となり、その後のデューデリジェンスや最終交渉の土台となる重要な工程です。
基本合意後、買い手は売り手企業の実態を詳細に調査します。小売業では、財務や法務に加え、各店舗の賃貸借契約、在庫の評価、POSシステムなどのITインフラ、店長やスタッフの能力といった事業面の調査が特に重要です。
この調査で発覚した問題点は、最終的な買収価格や契約条件に反映されるため、M&Aの成否を左右する重要なプロセスです。
デューデリジェンスの結果を踏まえて最終的な条件交渉を行い、双方が合意すれば、法的な拘束力を持つ最終契約書(株式譲渡契約書など)を締結しましょう。
その後、契約内容に基づき、株式や資産の引き渡しと対価の支払いを行う「クロージング」を実行します。これにより、経営権が正式に買い手に移転し、M&A取引が法的に完了します。
M&Aの成否を最終的に決定づけるのが、契約後の統合プロセス(PMI)です。小売業では、異なる店舗の従業員の意識統一、POSシステムや物流網の統合、仕入れの共通化などを計画的に進める必要があります。
特に、現場で働く従業員のモチベーションを維持し、円滑な協力体制を築くことが、期待したシナジー効果を生み出すための最も重要なポイントです。
小売業のM&Aに関するよくある質問
以下では、小売業のM&Aを進める上で寄せられることの多い質問とポイントを整理しています。
- M&A後、各店舗の運営方針やブランドはどのように扱われますか?
-
M&A後の店舗運営方針やブランドの扱いは、M&Aの目的によって「ブランド転換・統合」「ブランド維持・独立運営」「ブランド併存・ハイブリッド」の3パターンに大別されます。
買収側のブランドに統一して効率化を図るケース、買収された側のブランド価値を活かして多角化を図るケース、両ブランドの強みを融合させて新たな価値を創出するケースなど、戦略に応じて最適な方法が選択されます。
- 取引先や仕入れ先との関係はM&A後も継続できますか?
-
M&A後も取引先との関係を継続できるかは、用いるM&A手法によって異なります。
会社の経営権ごと移転する「株式譲渡」では、契約関係は原則としてそのまま引き継がれます。一方、事業の一部を売買する「事業譲渡」では、取引先との契約は個別に結び直す必要があり、相手方の同意が得られないと契約が継続できないリスクがあるため、注意が必要です。
M&Aによる引継ぎをサポートしてくれるM&A仲介会社はあります。どの仲介会社がおすすめか無料で知りたい方は「M&A比較ナビ」に相談してみてください。