「後継者がおらず、会社の将来が不安だ」
「会社の成長のため、M&Aを検討しているが何から始めればいいかわからない」
本記事では、SES業界のM&Aについて、その動向から価格相場、具体的なメリット、成功のポイントまでを網羅的に解説します。
この記事を読めば、SES業界におけるM&Aの全体像を理解し、事業承継や事業拡大に向けた具体的な第一歩を踏み出すための知識が身につくはずです。
SES業界のM&Aとは
SES(システムエンジニアリングサービス)業界では、M&Aが近年活発化しています。
SESとは、クライアント企業にエンジニアの技術力を提供するサービスモデルを指します。具体的には、準委任契約に基づき、エンジニアがクライアントの現場に常駐してシステム開発や運用を支援することです。
SESのビジネスモデルの核心は「人材」そのものが商品である点です。そのため、企業の価値は在籍するエンジニアの数や質に大きく依存します。
SES業界でM&Aが活発な最大の理由は、深刻なIT人材不足です。自社採用だけで必要なエンジニアを確保することが年々難しくなるなか、M&Aは優秀な人材を迅速に確保する有効な手段となっています。
また、経営者の高齢化に伴う後継者問題の解決策や、異業種がDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進するためにIT機能を内製化する目的でSES企業を買収するケースも増えています。
SES業界のM&Aと他業界との違い
SES業界のM&Aは、在籍するエンジニアの「数」と「質」が企業価値に直結する点が最大の違いです。
工場の設備や不動産といった物理的な資産ではなく、エンジニア一人ひとりのスキルや経験、顧客との契約単価が会社の値段を決めます。そのため、M&Aの際には、人材のスキルセットや稼働率が厳しく査定されます。
また、買収後のエンジニアの離職リスクが他業界に比べて特に高いという課題も抱えています。客先常駐という働き方の特性上、エンジニアの自社への帰属意識が育ちにくく、M&Aによる環境変化を機に退職を選ぶケースが少なくありません。
さらに、近年は異業種によるDX内製化を目的とした買収が多いのも特徴的です。これは、IT開発力を迅速に取り込みたいという外部の強いニーズを反映しています。
SES業界のM&Aの価格相場
SES企業のM&Aを検討するうえで、自社の価値がどれくらいになるのか、その価格相場を知ることは非常に重要です。
M&Aにおける企業価値は、一般的に用いられる計算式をベースにしつつ、SES業界ならではの「人材価値」という指標を加えて総合的に評価されます。
M&Aにおける企業価値は、一般的に会社の純資産に、営業利益の3年〜5年分を「のれん代(企業の将来性や技術力、顧客基盤などの無形資産価値)」として上乗せして算出されます。
例えば、純資産が5,000万円、年間の営業利益が2,000万円の企業であれば、「5,000万円 + (2,000万円 × 3年~5年) = 1億1,000万円~1億5,000万円」が簡易的な目安です。
しかし、SES業界ではこの「のれん代」を算出するうえで、エンジニアの人数、保有スキル、稼働率といった業界特有の指標が大きく影響します。
AIやクラウドなどの先端技術を持つエンジニアが多数在籍していたり、高い稼働率を維持していたりすると、企業の将来性が高いと評価され、営業利益の5年分、あるいはそれ以上の価格で取引される可能性もあります。まさに「人が資本」であることを示す評価方法です。
SES業界M&Aの最新動向がわかる3つの成功事例
近年、SES業界では事業拡大や人材確保、DX推進などを目的としたM&Aが活発に行われています。
ここでは、SES業界のM&Aの動向を理解する上で参考となる3つの具体的な事例をご紹介します。
それぞれの背景や目的を知ることで、自社のM&A戦略を考える上でのヒントが見つかるでしょう。
cottaによるTERAZの子会社化
製菓・製パン材料のECサイトを運営する株式会社cottaは、2024年にシステム開発会社の株式会社TERAZを子会社化しました。
これは、異業種の企業がDX推進とIT人材確保のためにSES企業を買収した典型的な事例です。
cottaは、ECプラットフォームの機能強化や物流システムの最適化を内製化するため、高い技術力を持つTERAZのエンジニア集団を獲得しました。外部に開発を委託するよりも、M&Aによって開発チームを自社内に持つことで、スピーディーな経営判断とシステム開発を実現する狙いがあります。
この事例は、SES企業がIT業界内だけでなく、幅広い業界から求められていることを示しています。
テンダによるリーサコンサルティングの子会社化
ITサービス企業の株式会社テンダは、2023年にITコンサルティングやシステム開発を手がける株式会社リーサコンサルティングを子会社化しました。
このM&Aの目的は、自社の技術力やサービス領域を強化することにあります。
テンダは、リーサコンサルティングが持つ業務改革コンサルティングのノウハウや、Salesforceなどの特定領域における高い技術力を獲得しました。これにより、既存のサービスと組み合わせることで、顧客に対してより付加価値の高いワンストップソリューションを提供できるようになります。
同業種間でのM&Aによって、お互いの強みを活かしたシナジー創出を目指す好例と言えるでしょう。
ISIDインターテクノロジーによるキャスレーコンサルティングからの事業譲受
株式会社電通国際情報サービス(ISID)グループのISIDインターテクノロジー(現 電通総研IT)は、2020年にキャスレーコンサルティング株式会社からSES事業の一部を譲り受けました。
この事例は、開発体制の強化を目的とした事業譲渡というスキームが活用された点が特徴です。
ISIDインターテクノロジーは、この事業譲受によって約50名のITエンジニアを獲得し、不足していた開発リソースを補強しました。会社全体ではなく、必要な事業部門だけを切り出して売買する事業譲渡は、買い手にとっては投資を抑えつつ必要な人材や事業を獲得でき、売り手にとってもノンコア事業を整理して主力事業に集中できるというメリットがあります。
SES業界のM&Aにおすすめの仲介会社・サービス3選
SES業界のM&Aを成功させるためには、業界特有の事情に精通した専門家のサポートが不可欠です。エンジニアの価値評価や契約関係の整理など、専門的な知見がなければ、思わぬ失敗につながりかねません。
SES・IT業界のM&Aに強みを持つ、おすすめの仲介会社・サービスは以下のとおりです。
以下では、それぞれの特徴を詳しく紹介します。
どの仲介会社に相談すべきか判断が難しい場合は、複数のサービスをまとめて比較できる「M&A比較ナビ」の活用が便利です。自分に合った支援先を見つけたい方は、まずは無料相談から始めてみてください。
株式会社パラダイムシフト

| 会社情報 | 詳細 |
|---|---|
| サポート内容 | ・M&A戦略立案 ・企業価値評価・候補先の選定 ・交渉・デューデリジェンス支援 ・契約書作成サポート |
| サポート体制 | ・IT業界に特化したコンサルタント ・豊富なM&A実績と独自ネットワーク |
| 料金体系 | ・要問い合わせ(一般的に成功報酬型) 取引規模別手数料率・最低保証額 1億円未満:3.0%(最低保証額:300万円) 1億円以上〜5億円未満:2.5%(最低保証額:500万円)5億円以上:2.0%(最低保証額:1,000万円) |
| 特徴 | ・IT業界、特にSES ・SIerのM&Aに特化 ・業界への深い知見と専門性 ・独自のネットワークによる最適なマッチング |
| 運営会社 | 株式会社パラダイムシフト |
| URL | https://paradigm-shift.co.jp/ |
株式会社パラダイムシフトは、IT業界のM&Aに特化した仲介会社です。SESやSIer(システムインテグレーター)のM&Aを数多く手がけており、業界のビジネスモデルや価値評価の方法を深く理解しています。
IT業界に特化しているからこそ、企業の技術力やエンジニアのスキルセットといった無形の価値を正しく評価し、最適な相手とのマッチングを実現できるのが最大の強みです。
専門性の高いコンサルタントが、戦略立案から交渉、契約締結まで一貫してサポートしてくれます。SES業界でM&Aを検討するなら、まず相談を検討したい一社です。
IT領域でのM&Aには強みを持っていて、業者ごとの買い手企業の情報は蓄積されている。そのため買い手探索は工数が割かれないようシステム化されている。
引用:OpenWork
営業熱心な会社で最後もまでフォローしていただきました。
ありがとうございます。引用:Google Map
営業メールお断りとかいてあるのに問い合わせフォームから送ってくる非常識な会社です。
引用:Google Map
株式会社M&Aサクシード
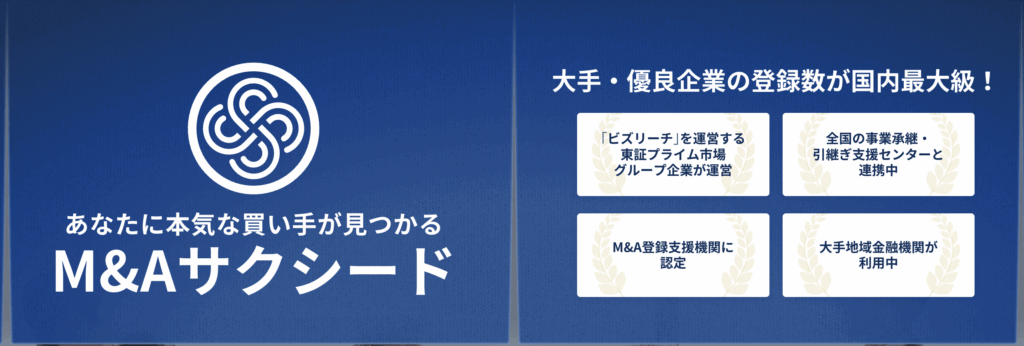
| 会社情報 | 詳細 |
|---|---|
| サポート内容 | ・M&Aマッチングプラットフォームの運営 ・法人・事業の譲渡、譲受の相手探し ・アドバイザーの紹介 |
| サポート体制 | ・全国の金融機関、M&A専門家との連携 ・オンラインでのサポート |
| 料金体系 | ・譲渡企業:登録・利用料無料 ・譲受企業:有料プランあり 手数料概要 基本料金:無料 成約時手数料譲渡企業:譲渡対価の5%(最低報酬額1,000万円) 譲受企業:譲渡金額の2%(最低金額200万円) 契約期間:半年ごとの自動更新 |
| 特徴 | ・オンライン完結型のM&Aマッチングプラットフォーム ・譲渡企業は完全無料で利用可能 ・匿名での交渉開始が可能 |
| 運営会社 | 株式会社M&Aサクシード |
| URL | https://ma-succeed.jp/ |
株式会社M&Aサクシードは、オンラインでM&Aの相手を探せるマッチングプラットフォームです。最大の魅力は、売り手(譲渡企業)が登録から相手探し、交渉までを無料で利用できる点にあります。
自社の情報を匿名で登録し、興味を持った買い手(譲受企業)からのアプローチを待つことができます。プラットフォーム上にはIT・通信関連の案件も多数掲載されており、自社のタイミングでM&Aを進めたい経営者にとって非常に便利なツールです。
まずは情報収集から始めたい、どのような企業が自社に興味を持つか知りたいという方におすすめのサービスです。
士気高く社会課題を解決しようという意識を持ち働いている方が多かった。
引用:OpenWork
かつて登録していたのですが、事情があり2年ほどペンディング状態でした。再びM&Aを考えるにあたって、タイミングよく連絡がきたのです。私たちの求めるものについて丁寧に答えてくれ、まさに渡りに船のような気持ちでした。
営業電話でガチャ切りされました
引用:Google Map
PROSES M&A(株式会社PROSES)

| 会社情報 | 詳細 |
|---|---|
| サポート内容 | ・SES事業に特化したM&A仲介 ・企業価値評価 ・交渉 ・契約サポート |
| サポート体制 | ・SES業界出身のコンサルタント ・業界特化の専門知識 |
| 料金体系 | ・要問い合わせ(一般的に成功報酬型) 完全成功報酬制の詳細 初期費用・月額費用:0円 中間で発生する料金:0円 不成立の時は:0円 取引価格等・手数料率 5億円以下の部分:5% 5億円超〜10億円以下の部分:4% 10億円超〜50億円以下の部分:3% 50億円超〜100億円以下の部分:2% 100億円超の部分:1% |
| 特徴 | ・SES業界に完全特化したM&Aサービス ・エンジニアの価値を最大化する評価 ・業界の慣習や契約形態に精通 |
| 運営会社 | 株式会社nem |
| URL | https://pro-ses-ma.com/ |
PROSES M&Aは、SES事業に完全に特化したM&A仲介サービスです。運営会社の代表自身がSES企業の経営経験者であるため、業界のビジネスモデルや課題、企業価値の源泉であるエンジニアの重要性を深く理解しています。
SES業界ならではの契約形態(準委任契約)や商慣習、エンジニアの単価や稼働率といった細かい部分まで踏まえたうえで、企業価値を最大化するサポートを提供してくれるのが強みです。
業界の「中の人」だからこそできる、きめ細やかで的確なアドバイスが期待できます。同業者ならではの安心感を求める方には最適なサービスと言えるでしょう。
SES業界のM&A動向(現状・課題・今後)
SES業界のM&A市場は、IT業界の構造的な変化とともに、常に動き続けています。M&Aを成功させるためには、現在の市場環境や課題、そして今後のトレンドを正確に把握することが不可欠です。
ここでは、SES業界のM&A動向について、「現状」「課題」「今後」の3つの視点から解説します。
【現状】IT人材不足を背景にM&Aが増加
現在のSES業界は、深刻なIT人材不足を解消するための手段として、M&Aの活用が一般化しています。
多くの企業が自社での採用活動に限界を感じており、必要なスキルを持つエンジニア集団を迅速に確保できるM&Aは、事業成長に欠かせない戦略です。
特に、AIやクラウド、セキュリティといった先端分野のスキルを持つエンジニアへの需要は高く、こうした人材を抱えるSES企業は買い手市場で高い評価を得ています。売り手にとっては、自社の価値を高く評価してもらえるチャンスが広がっている状況と言えます。
【課題】客先常駐に起因するエンジニアの離職リスク
M&Aの増加に伴い、客先常駐という働き方に起因するエンジニアの離職リスクが大きな課題です。
エンジニアは日常業務を自社ではなくクライアント先で行うため、自社への帰属意識が希薄になりがちです。そのため、M&Aによる経営陣の交代や環境の変化をきっかけに、不安を感じて退職してしまうケースが後を絶ちません。
M&Aを成功させるためには、買収後の統合プロセス(PMI)において、エンジニアと丁寧なコミュニケーションを取り、待遇やキャリアパスについて安心感を与えることが極めて重要になります。
【今後】DX内製化や上流工程強化を目的としたM&Aが加速
今後のSES業界のM&Aは、単なる「人数の確保」から、より戦略的な目的を持つものが増えていくと予測されます。
その一つが、異業種による「DX内製化」を目的としたM&Aです。企業の競争力を左右するITシステムを自社でコントロールしたいというニーズは、今後ますます高まるでしょう。
また、IT業界内でも、多重下請け構造から脱却し、より利益率の高い「上流工程(コンサルティングや要件定義)」を強化するためのM&Aが加速します。特定の技術や業務ノウハウに強みを持つ、専門性の高いSES企業への注目がさらに集まる見通しです。
SES業界におけるM&Aの主要スキーム2選
SES業界のM&Aを進める際には、主に2つの手法(スキーム)が用いられます。
どのスキームを選択するかによって、手続きの進め方や税金、従業員の契約関係などが変わってくるため、それぞれの特徴を理解しておくことが重要です。
SES業界のM&Aでよく用いられる代表的な2つのスキームは以下のとおりです。
それぞれのスキームについて、わかりやすく解説します。
株式譲渡|会社全体を売買する最も一般的な手法
株式譲渡とは、売り手企業の株主が保有する株式を買い手企業に売却し、経営権を移転させる手法です。
手続きが比較的シンプルで、会社を丸ごと引き継ぐため、従業員の雇用契約や取引先との契約関係も基本的にはそのまま維持されます。
SES業界のM&Aにおいては、この株式譲渡が最も多く用いられるスキームです。後継者不在の解決策として会社全体を譲渡したい場合や、買い手が許認可を含めて事業全体をスムーズに引き継ぎたい場合に適しています。
従業員にとっても、所属する会社名が変わるだけで、雇用が継続される安心感があります。
事業譲渡|特定の事業部門のみを売買する手法
事業譲渡とは、会社の事業の一部または全部を選択して売買する手法です。
例えば、「Web開発事業部だけを売却する」といった形で、特定の資産や負債、人材、契約などを個別に選んで譲渡します。買い手にとっては、必要な事業だけを獲得できるため、簿外債務などを引き継ぐリスクを避けられることがメリットです。一方、売り手にとっては、不採算事業を切り離して主力事業に集中するための資金を得るといった活用が可能です。
ただし、従業員の転籍には個別の同意が必要になるなど、株式譲渡に比べて手続きが煩雑になる側面もあります。
SES業界でM&Aを活用するメリット
SES業界でM&Aを活用することは、会社を譲渡する側(売り手)、譲り受ける側(買い手)の双方にとって、多くのメリットをもたらします。
後継者問題の解決や事業の安定化、そして新たな成長機会の創出などは、自社の未来を切り拓くための強力な選択肢です。
ここでは、それぞれの立場から見た具体的なメリットを解説します。
【譲渡側】多重下請け構造から脱却し、より上流の案件に参画できる
中小のSES企業にとって、M&Aは業界特有の多重下請け構造から抜け出す大きなチャンスとなります。
大手IT企業や事業会社の傘下に入ることで、これまで受注が難しかったプライム案件(元請け案件)や、より上流工程のコンサルティング、要件定義といった高付加価値な業務に携わる機会が生まれます。
これにより、エンジニアは自身のスキルをより高度なレベルを活かせ、キャリアアップにも繋がります。会社の利益率が向上するだけでなく、エンジニアのモチベーション向上や定着率アップという好循環が期待できるのです。
【譲渡側】エンジニアの雇用安定とキャリアパスを確保できる
後継者不在や経営環境の変化に悩む経営者にとって、従業員であるエンジニアの雇用を守り、将来のキャリアを安定させることは最大の関心事です。廃業を選択すれば、従業員は職を失ってしまいますが、M&Aによって経営基盤の安定した企業のグループに入ることで、彼らの雇用を維持できます。
さらに、大手企業の豊富な研修制度や多様なプロジェクト、明確なキャリアパス制度などを活用できるようになるため、エンジニア一人ひとりが成長できる機会も増えます。
M&Aは会社を存続させるだけでなく、大切な従業員の未来を守るための有効な手段なのです。
【譲受側】新規顧客や特定領域の技術やノウハウを獲得・事業領域を拡大できる
買い手企業にとって、M&Aは自社が持たない新たな顧客基盤や、特定の技術領域に関するノウハウを一気に獲得できる絶好の機会です。
例えば、金融業界に強い顧客網を持つSES企業を買収すれば、その販路を自社サービスにも活用できます。
また、AIやクラウド、特定の業務システムに関する高い専門性を持つ企業を取り込むことで、自社のサービスラインナップを拡充し、対応できる事業領域を大きく広げることが可能です。ゼロから新しい事業を立ち上げるのに比べて、時間とコストを大幅に節約しながら、確実な事業拡大を実現できる点が大きなメリットです。
【譲受側】優秀なエンジニア集団を迅速に獲得できる
現在のIT業界において、優秀なエンジニアを採用することは極めて困難であり、M&Aは最も確実かつスピーディーな人材獲得戦略と言えます。特に、チームとして機能しているエンジニア集団をまとめて獲得できる点は、M&Aならではの大きな利点です。
一人ずつ採用してチームを組成するには長い時間と多大なコストがかかりますが、M&Aであれば、すでに連携の取れた開発チームを即座に自社の戦力として加えられます。
これにより、新規プロジェクトの立ち上げや、既存事業の拡大を速やかに進められ、市場での競争優位性を高めることに直結します。
SES業界でM&Aを成功させるポイント・注意点
SES業界のM&Aは多くのメリットがある一方で、成功のためには業界特有のポイントを押さえることが必要です。
特に「人材」と「契約」に関する注意点を軽視すると、期待した効果が得られず、M&Aが失敗に終わるリスクもあります。
ここでは、譲渡側・譲受側それぞれの立場で特に注意すべき点を解説します。
【譲渡側】取引先との契約内容を整理し、M&A後の契約維持の見通しを立てる
譲渡側(売り手)がまず行うべきことは、主要な取引先との契約内容を正確に把握し、整理しておくことです。
SES事業の契約には、経営者が変わる際に相手方の承諾が必要となる「チェンジオブコントロール(COC)条項」が含まれている場合があります。COC条項を見落としていると、M&A後に契約を打ち切られてしまい、会社の売上が激減する恐れがあります。
事前に契約書を全て確認し、必要であれば取引先にM&Aの可能性を打診しておくなど、契約が維持される見通しを立てておくことが、自社の価値を正しく評価してもらい、M&Aをスムーズに進めるための重要なポイントです。
【譲渡側】M&A後の労働条件を明確にし、エンジニアの離職を防ぐ
譲渡側経営者の責任として、エンジニアたちがM&A後にどのような労働条件や労働環境になるかを、買い手側と事前にきちんと協議し、明確にしておくことが極めて重要です。
給与や福利厚生、勤務地、担当するプロジェクト内容など、具体的な情報を可能な限りエンジニアに開示し、不安を取り除く努力が求められます。
M&Aの成立を優先するあまり、従業員の処遇を曖昧にしたまま進めてしまうと、M&A成立後に大量離職を招き、結果的に会社の価値を大きく損ないます。エンジニアの生活を守るという強い意志を持って、交渉に臨む姿勢が不可欠です。
【譲受側】経営層・トップエンジニアの引き留めを徹底する
譲受側(買い手)にとって、買収する会社の価値の中核をなす経営層やトップエンジニアの引き留め(リテンション)は、M&A成功の最重要課題です。
特に、創業者である社長や、技術面・顧客関係で中心的な役割を担うキーパーソンがM&A直後に退職してしまうと、事業の継続が困難になることさえあります。
そのため、M&Aの交渉段階から、キーパーソンに対してM&A後の役職や待遇、権限などを魅力的な条件で提示し、一定期間は会社に残ってもらう約束の取り付けが重要です。これを「キーマン条項」として契約に盛り込むことも一般的です。
【譲受側】事業や組織文化の統合(PMI)を計画的に行い、シナジーを最大化する
M&Aは、異なる歴史や文化を持つ2つの会社が1つになるためには、PMI(Post Merger Integration:M&A後の統合プロセス)の計画的で丁寧なすり合わせが必要です。
人事評価制度や会計システムといった制度面の統合はもちろん、お互いの企業文化を尊重し、従業員同士のコミュニケーションを促進する場を設けるなど、組織文化の統合にも力を入れる必要があります。
このPMIを疎かにすると、社内に軋轢が生まれて従業員のモチベーションが低下し、期待したシナジー(相乗効果)が全く得られないという結果に終わってしまいます。
SES業界でM&Aを実施する8つの手順
SES業界のM&Aは、一般的に以下のような手順で進められます。
全体の流れを把握しておくことで、各段階で何をすべきかが明確になり、スムーズな進行につながります。専門的なプロセスも含まれるため、M&A仲介会社などの専門家と連携しながら進めるのが一般的です。
まずは、自社の経営課題(後継者問題、エンジニア採用難、多重下請け構造からの脱却など)を解決するために、M&Aが本当に最適な選択肢なのかを慎重に検討します。M&Aの目的や希望する条件(売却価格、エンジニアの雇用とキャリアパスの維持など)を明確にし、基本的な戦略を立てることが全ての始まりです。この段階でM&Aの専門家に相談し、客観的なアドバイスを求めることが成功の鍵となります。
どの会社に相談すべきか迷う場合は、「M&A比較ナビ」のようなサービスを活用して、自社に合ったアドバイザーを見つけるのも良いでしょう。
M&Aを本格的に進めることを決めたら、サポートを依頼するM&A仲介会社とアドバイザリー契約を締結します。特にSES業界のM&Aでは、業界のビジネスモデルやエンジニアの価値評価に精通した専門家を選ぶことが極めて重要です。契約内容や料金体系(着手金、成功報酬など)をよく確認し、自社の状況を深く理解してくれる信頼できるパートナーを選びましょう。
仲介会社の協力のもと、自社がいくらで売却できる可能性があるのか、企業価値評価を行います。SES業界では財務諸表の数字に加え、在籍エンジニアの人数、スキルセット、稼働率、平均単価などが企業価値を大きく左右します。並行して、買い手候補に自社の魅力を伝えるための資料「インフォメーション・メモランダム(IM)」を作成します。IMには、主要エンジニアのスキルやプロジェクト実績、主要顧客との契約形態などを具体的に記載し、人材の価値をアピールします。
仲介会社が、設定した条件に基づき、シナジーが見込める買収候補企業(買い手)をリストアップします。候補には同業のSES/SIerだけでなく、DXを推進したい異業種の事業会社も含まれます。最初は社名を伏せた「ノンネームシート」で候補企業に打診し、関心を示した企業との間で秘密保持契約(NDA)を締結した後、詳細な企業情報を開示し、具体的な交渉を開始します。
交渉がある程度進んだ段階で、売り手と買い手の経営者同士が直接会って話をする「トップ面談」が行われます。ここでは、お互いの経営理念やビジョンに加え、M&A後のエンジニアの処遇(給与、キャリアパス、働き方)や企業文化のマッチングについて深く話し合います。双方がM&Aに前向きであることが確認できたら、譲渡価格やスケジュールといった基本的な条件をまとめた「基本合意契約(LOI)」を締結します。
基本合意契約を締結した後、買い手側が売り手企業の価値やリスクを詳細に調査する「デューデリジェンス(DD)」を実施します。SES業界のDDでは、財務や法務に加えて、エンジニアとの雇用契約の内容、主要顧客との基本契約や個別契約の精査、偽装請負などの労務リスクの有無、エンジニアの稼働状況の実態調査などが特に重要なチェックポイントとなります。
デューデリジェンスの結果を踏まえ、最終的な譲渡価格や従業員の処遇、役員の退職条件など、契約の詳細について最終交渉を行います。SES業界のM&Aでは、主要顧客との契約がM&A後も維持されることや、キーとなるエンジニアが一定期間在籍すること(キーマン条項)などを契約内容に盛り込むことが一般的です。全ての条件について双方が合意に至ったら、法的な拘束力を持つ「最終契約(DA)」を締結します。
最終契約書に定められた条件に従い、株式や事業の引き渡しと、対価の支払いを行います。この「クロージング」をもってM&Aの法的な手続きは完了しますが、本当の成功はここから始まります。SES業界のPMI(経営統合プロセス)では、エンジニアの離職を防ぐことが最重要課題です。人事評価制度や給与体系の丁寧なすり合わせ、両社エンジニア間のコミュニケーション促進などを計画的に行い、円滑な経営移行とシナジーの最大化を目指します。
SES業界のM&Aに関するよくある質問
最後に、SES業界のM&Aを検討している経営者の方からよく寄せられる質問にお答えします。M&Aは専門的な内容が多く、疑問や不安を感じる点も多いかと思います。
ここで具体的な疑問点を解消し、次の一歩を踏み出すための参考にしてください。
- 赤字のSES企業でも売却は可能ですか?
-
赤字であっても売却できる可能性は十分にあります。
M&Aの評価は、現在の財務状況だけでなく、将来性や保有している技術、人材、顧客基盤なども総合的に判断されるためです。例えば、特定の先端技術を持つエンジニアが多数在籍している、あるいは大手企業との強固な取引関係があるといった場合は、赤字を補って余りある魅力として評価されることがあります。
ただし、買い手側は赤字の原因を厳しく精査します。それが一時的なものなのか、構造的な問題なのかによって評価は大きく変わります。自社の強みと課題を正確に分析し、将来性をアピールすることが重要です。
- 主要な取引先が1社に集中していますが、売却に影響はありますか?
-
影響はあります。一般的に、取引先が分散している方がリスクが低いと評価されます。
特定の1社への売上依存度が高いと、その取引先との契約が終了した場合に経営が立ち行かなくなるリスクがあると見なされるためです。M&Aの交渉において、企業価値評価が低くなる要因となる可能性があります。
しかし、その取引先が非常に安定した大企業であったり、長期にわたる強固な関係性が証明できたりすれば、マイナス評価を軽減できる場合もあります。この点についても、M&Aの専門家と相談しながら、どのようにアピールしていくか戦略を練ることが大切です。
- M&Aの際、客先常駐しているエンジニアの契約はどうなりますか?
-
M&Aのスキームによって扱いが異なりますが、基本的には契約関係が維持されるように手続きが進められます。
最も一般的な「株式譲渡」の場合、会社の法人格はそのまま維持されるため、従業員の雇用契約や顧客とのSES契約も原則としてそのまま引き継がれます。エンジニアは、所属する会社の株主が変わるだけで、基本的には同じ顧客先で業務を継続することになります。
ただし、顧客との契約書に経営権の変更に関する条項(チェンジオブコントロール条項)がある場合は、顧客の事前承諾が必要になるケースもあります。M&Aを進めるうえでは、こうした契約内容の確認が非常に重要です。
もし判断に迷う場合は、複数の仲介会社を比較検討できる「M&A比較ナビ」などを活用し、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。完全無料で利用できるため、まずは気軽に相談してみてください。